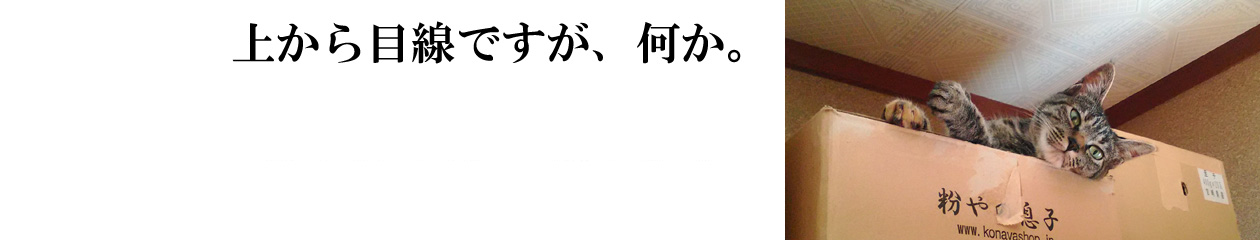「ガスファンヒーター、買おうと思ってるねんけど」
知り合いの方が僕にそう言う。なんでも毎年、冬を越すのにエアコンと電気カーペットと炬燵ですごしており、電気代が高くなると困ってたので、お勧めしていたのだ。
「いやでも確か前に、石油とかガスとか使うのは怖いって、言ってませんでしたっけ?」
「ガスはええかなって」
「ガスはええんですか」
「石油は臭いから嫌」
「回答になってませんけど・・・」
「ガスやけど、爆発せぇへんやんな? バーンって」
「知りませんよ。ガス屋に相談して下さい。でも、エアコンと違う燃料系ファンヒーターの利点は・・・」
ガスや石油は燃えると、二酸化炭素と水を発生させる。そのおかげで加湿効果も見込める。加湿されているとほのかに暖かく感じる。
ただ、石油ファンヒーターは灯油の補充が必要だ。買いに行くのも、補充するのも面倒だ。タンクは結構重いし、お年寄りなどには持ち運びが大変。
「・・・ガスはその点、楽ですからね。ホースで元栓に繋ぐだけで、延々と燃料が補給される」
「そう。それで何買ってええか分からへんから、ええの教えてくれへん?」
「分かりました。父親の体が動かしにくくなったので、うちもガスファンヒーターにしようと考えてたところです」
* * *
我が家の暖房は、灯油歴が長い。
ずっと石油ストーブの上にやかんをのせていた。母は、おでんを仕込んだらずっとその上に乗せていた。家じゅうがおでん臭くなっていたものだったが、確かに効率は良い。
石油ファンヒーターは、おそらく出始めの頃から使っている。学校へ行ってた頃は、着替える服が冷たくて、ファンヒーターから出てくる温風を服の中に入れてから着ていた。朝のファンヒーター前は、兄弟で陣取り合戦であった。
当時、灯油は酒屋さんの配達で調達していたと思う。
それがなくなってからは、両親は町に軽トラックで配達しにくる灯油訪問販売業者から買っていた。
僕は大音量で騒々しく巡回する彼らをあまり快く思っていなかったので、車で出かけるついでがあれば、灯油缶を搭載しつつガソリンスタンドに買いに行ってあげていた。
父が脳梗塞で入院し、身体が動かしにくくなった。
今まで父は、灯油訪問販売業者から毎週灯油缶二つ分を購入し、ストーブとファンヒーターで暖を取っていた。
だがもう、玄関先まで灯油缶二つを持っていき、重い灯油缶を家まで持って入るのは難儀だろう。
何より、片方の手足が動かしにくい状況では、灯油をタンクに入れるという一連の動作の中で、こぼしてしまう可能性が高い。面倒くさくなって、暖を取ることをしなくなってしまっては、元も子もない。
一気に寒くなった時期、父の脳の細い血管は詰まってしまった。暖かい時期には大丈夫だった。身内にこのような事が起こってしまっては、人間にとって「寒さ」は身体に大きなストレスを与えているのだと実感せざるを得ない。
実家は昭和の古い造りなので、キッチンにも和室にもガス管が通っている。ホースをカチッと差し込めるタイプのものだ。そこでガスファンヒーターを使うことができるだろう。
色々と見ていると、値段もそれなり。どの機器を買っても大差はなさそうだった。奈良の山奥は高いプロパンガス一択だけど、実家は都市ガスだから、値段も灯油とそれほど変わらないはずである。
独居老人の独自判断ほど、やっかいなことはない。
父が倒れ、国外単身赴任中の兄は、一時帰国してきた。
長男として、介護の責任と重圧を感じ、病院に見舞いに来ている。兄と一緒に、今後の父の生活をどうするかという事で、話し合っている。
その横で父はベッドに横たわって、大相撲の中継を見てのんびりしている。
好き嫌いの多い父は、人の忠告も聞かないで、自分の好きな物ばかりを長年食べてきた。それもインスタント食品ばかり。医師にはその事をとがめられてきたが、改善しようと努力するかと言えば全くしない。好き勝手生きて病に倒れたのはこれで二回目だ。周囲に面倒をかければ、再度倒れないよう気に掛けるべきなのに、その努力より自分の欲求を優先する。そのくせ倒れたら、俺はもうだめだと悲観する。
ダメ人間の典型である。
僕は、帰国してまで面倒を見る必要はない、と兄に言った。だが、兄はそういう訳にはいかないと言う。
僕はと言えば、「てめぇの長年の不摂生で勝手に倒れて、真面目に働いている兄きに多大な迷惑かけてるんだから、よく身に染みて謝っとかないと俺が許さないからな」と病床の父を脅した。
兄は僕と違って「優しい人」なのだ。
僕は、自分勝手な人間が、当然のように「優しい人」の恩恵を被り、無自覚でいることが我慢ならない性格なのだ。
「ありがとう」を言わない人間は、無自覚だ。自覚があるなら、もっとたちが悪い。
* * *
夕刻。
仕事終わり、誰もいなくなった実家に帰る。
灯油訪問販売業者の車が、著作権を無視したテーマソングで巡回している。
車と家を往復し、荷物を積み込んでいると、灯油訪問販売業者の軽トラックが、家の前でずっと停車している。
何だろうか。ご近所さんが灯油缶を出している気配もない。実家の灯油はもう僕が車で補充するようにしているので、買う気もない。
横目に玄関のカギを閉めていると、
「すいません」
細身で眼鏡をかけた年配の男性が、軽トラックから降りてきて、僕に話しかけてきた。朴訥とした、礼儀正しい人だった。
「はい。何ですか」
「突然ですいません。私、長年お父様から灯油を毎週買っていただいていた者なのですが、最近お父様をお見かけしなくなっておりましたので、気になって声をかけてしまいました」
すいません、ともう一度、男性は僕に謝罪した。
「ああ、そうなんですか。父は今、体調を崩して、入院しているのです。それでこの家にはいないんです」
「ああ、そうなんですか・・・」
「脳梗塞で、体が半分動かなくなりまして」
男性はその言葉を聞いて、大層なショックを受けたようだった。
父は、例外を嫌う人間だ。
一度決めたパターンを崩されることを、異様に嫌う。
なので、一度決めたこの灯油訪問販売業者から、値段も何も考えずに、何年も何年も買い続けていたのだろう。
ガスファンヒーターに変える予定だったので、もう父が独自に灯油を買うことはない。父は結構な量の灯油を買っていたはずなので、売り上げは結構落ちるだろう。はっきり断ってガッカリさせるのも忍びない。
「なので、また父親が退院して、体が動くようになったら、お願いするかもしれませんけど・・・」
ていよく長年の慣習を断とうとした僕に、
「いえいえ、そんなことはどうでもいいんです」
と男性は言葉を遮った。
「灯油を買っていただくとか、そんなことはどうでもいいんです。お父様の命が無事だったことが、何より一番なんです」
そういいながら、何に拝んでいるのか、男性はずっと胸の前で両手を併せている。
「退院されても、うちで灯油を購入していただくとか、そんなことはしていただかなくて結構です。ただ、ご無事で良かったとだけお伝え下さいませんか」
僕は、自分の先入観を幾分恥じた。この男性は、ただ灯油をうちに売りたいだけなのだろうと、邪険に扱おうとしていた。
この男性は灯油以外にも、昔ながらの「何か」を、売っていた人だった。
「あ、はい。ありがとうございます」
頭を下げた。
「そんな、頭を下げないで下さい。身体が大事ですから。命が何より大事ですから」
そう言ってずっと、男性は何かに拝むように、胸の前で両手を揃えていた。
* * *
病院のロビーで、兄と合流した。
今後の介護の方向性や、自分たちが何をすべきかなど、話し合うためだ。
石油ファンヒーターをやめて、ガスファンヒーターを買おうと思う、そうすればスイッチ一つで即暖房だし、燃料補充がいらないからと兄に言った後、
「でもな」
さきほど遭遇した、灯油訪問販売業者の話をした。
「ええ人やな」
「ええ人やろ。それで、石油ファンヒーターは確かに面倒やし、体がどこまで回復するか分からへん親父には難儀やろうと思うねんけど、その灯油販売の男性に俺から言うて、灯油缶を家まで上がって補充してもらうというのも、アリかなと思って」
「そうやな。親父は引きこもって誰とも会話せぇへんし、その人なら喜んで交流してくれるかもな」
「俺、少しその男性の優しさに感動したから、すぐ病院行って親父に顛末を話してん」
「うん」
「親父、『そんな人知らん』って」
「・・・マジか」
「ほら、眼鏡かけて細身でって必死に説明したけど、無言で頭振ってた」
「・・・台無しやな、親父」
うちの父は、基本的に他人に興味がない。向こうが親しみを持ってくれるほど長い年月、週に一回とはいえ交流があったとしても、父にとっては相手の顔を覚える必要がない程度のものだったのだ。
息子からすると、大いにあり得る話ではあるが、そこは知っていて欲しかったし、「ありがたい」と感謝して欲しかった。
もう一度書くが、僕は自分勝手な人間が、当然のように「優しい人」の恩恵を被り、無自覚でいることが我慢ならない性格なのだ。
「ありがとう」を言わない人間は、無自覚だ。自覚があるなら、もっとたちが悪いが、無自覚な父に関しては首の皮一枚残して我慢している。
世の中は、「優しい人」と「優しくない人」に別れている。
優しい人だけで、世の中は回らない。今の世の中は、そういうもので溢れかえっているので、優しいだけで生きていける時代ではない。その傾向は、これからどんどん顕著になっていく。
そういう未来を選んだのは、僕たちだ。
優しい人でも、生きて行くために優しくない振りをして人を傷付けなくてはならない時もある。そういう人は、日々ストレスを抱え込んでいるかもしれないが、結果として人に優しくできないどころか傷付けているのだから、同罪だと思っている。
「根は優しい人だから」と言って許すことは、その人の為にならない。人はおおよそ、根は優しくできているからだ。
灯油訪問業者の男性は、灯油ともう一つ、「何か」を売っていたのだろう。
昔の対面販売が当たり前だった日本では、普通に売っていた「何か」を。田舎に住む僕には、それが少し分かる。
便利な社会は効率を優先し、不便さを置き去りにしていく。
そうして出来上がった効率的な社会は、不便さや面倒くさいことからしか収穫できない、目に見えないものを考慮せず、無自覚になる。無自覚に何も考えず、色々なものを踏みにじる社会になっていく。
できるなら僕は、優しい人達に囲まれて暮らしたいと思う。
優しい人に囲まれて暮らすために、落ちぶれて滅びることがあるとするならば、それは納得して受け入れようと思う。
随分前から、交友関係は「優しい人」で判定するようにしている。
僕は決して「優しい人」ではないけれど、「優しい人」に敬意を持ち、感謝して、なるべく踏みにじらないようにしながら生きていきたい。
こうして。
一度は、父の「人との交流を生む」という石油ファンヒーターの思わぬ利点に心動いた僕だったが、無自覚な父に踏みにじられ、結局ガスファンヒーターに買い替える案が採用されたのだった。
得てして。世の中こんなもんでは、あるけれど。
僕が実家にいる間は石油ファンヒーターを残しておいて、灯油訪問業者の男性から灯油を買うようにしようか、などと。
何となく思っている。