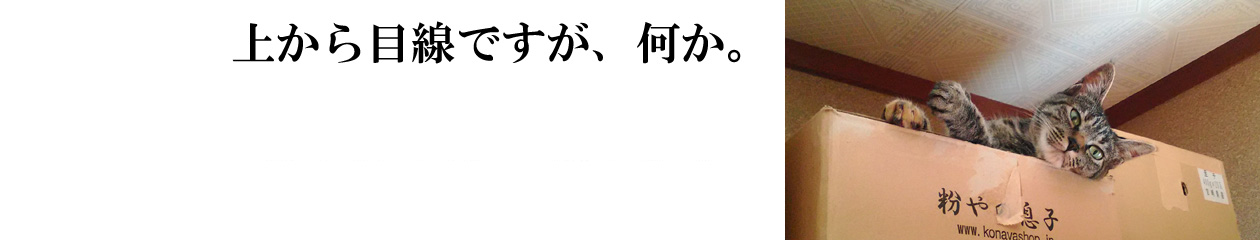二歳半の娘には、まだ自分一人ではできないことが沢山ある。
例えば、ビンの蓋を開けるとか。難しいパズルをやってみるとか。
そんな時は、
「父ちゃん、これやって!」
と僕にせがむ。
せがむというか、命令する。
父親として、それをしてあげることが誇らしく、また嬉しいことでもある。
その娘が産まれる少し前、僕の父が散歩中に倒れ、頭を強打し、救急車で病院に運び込まれた。冬の一番寒い時期だった。
幸い命に別状はなかったが、父は長引く入院生活の中で、すっかり生きる気力を失ってしまった。
娘が産まれた後も、父の入院生活はしばらく続いた。僕ら家族は当時、父と同じ家で一緒に生活していたので、入院時の世話から送り迎え、費用の段取りから何からすべて僕らが面倒を見ていた。
奥さんは産まれたばかりの一人娘の世話でてんやわんやだったと思う。
僕の母親はすでに他界しており、面倒を見ることができるのは僕らしかいない。僕は僕で仕事が忙しい。なのに、いつまでたっても生きる気力を一向に見せない父親にイライラし、つい語気荒げて父に怒鳴ることも、しばしばあった。
「死んだ母ちゃんは不治の病やったけど、最期の最期まで、諦めずに頑張ってたやないか。それを一番近くで見てたんは、つきっきりで看病してたオヤジやろうが。オヤジの病気は治らんモンやない。そやのに何で、生きようと思わへんねん」
――母ちゃんに恥ずかしいと思わへんのか。そんなことも思えないようなら、死んでしまえ。
あまりに腹が立って、病室で怒鳴り散らしてしまうこともあった。
「子供が産まれたら、おじいちゃんとして色々手伝ってくれ」
と僕が言うと、「よっしゃ」と笑いながら答えていた父。
病に倒れ、病院に運び込まれ、二度の手術を経て家に戻ってきた日から、誰とも会おうともせず、一日中家に閉じこもるようになった。ことあるごとに僕も声をかけるようにしていたが、父の心には、響かなかった。
言葉もしゃべれなかった娘もやがて成長し、よちよち歩きができるようになった頃。僕ら一家は、大阪から引っ越した。
娘は見ず知らずの人に抱かれると泣き、知っている人でも一週間会わなければ抱っこされると泣いた。立派な人見知りに育った。
月に一二度大阪の実家に帰ると、その人見知りの娘も、おじいちゃんには近寄っていく。近寄って行っては、ソファに並んで一緒にテレビを見たりしている。
「おじいちゃん、すき」
娘が恥ずかしそうにそう言った。
父は何とも言えないような、照れくさいんだか何だか分からないような顔をした。
「おじいちゃんのこと、好きなんか」
「うん」
「そうか」
父はそう言って押し黙ったまま、何か考え込むように娘を見つめていた。
やがて、父は散歩を再開した。相変らず夕飯を食べるとすぐ寝室へ行って寝っころがりながらテレビを見るが、見ながら軽めの鉄アレイでトレーニングをするようになった。
人に、前向きな気持ちを持ってもらうことは、とても難しい。
「生きろ」
という言葉は、何だか嘘くさい。
娘はイヤイヤ期に突入し、益々生意気になったけど。おじいちゃんのことは変わらず好きなようだった。
あいかわらず、ビンの蓋をあけられなかったり、難しいパズルがあったときは、
「父ちゃん、やって」
と僕にせがむというか、命令する。
父ちゃんは、君がまだまだ何もできないことを、よく知っている。
父ちゃんが手伝えるときは父ちゃんが、母ちゃんが手伝えるときは母ちゃんが、君を助けてあげている。
でもね。
父ちゃんにはできない、「君にしかできないこと」があることも。父ちゃんは、ちゃんと知っている。
君はおじいちゃんに、「生きよう」と思わせてくれた。
それは父ちゃんがどれだけ頑張っても、おじいちゃんに思わせることができなかったことなんだ。
どうもありがとう。これからもよろしく。
(了)
* * *
娘が二歳半のころの、エッセイコンテストに応募しようと書いた文章を見つけ、折角なのでアップしてみた。
文字数制限内にどうしても収めることができず、文字数を削ってしまうと伝えたいことも削れてしまう気がして、なんとなくお蔵入りにしていた。
その頃と今の状況は、色々と変化しているけれど、書いた時の気持ちは、忘れてなるまいと思った。