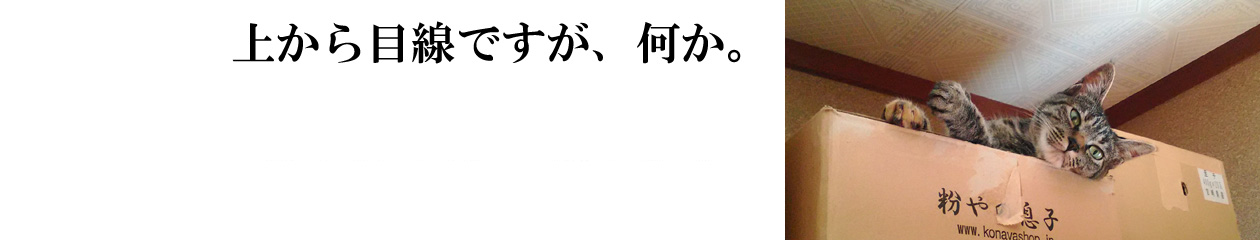娘とも、もう5年の付き合いになった。
娘にとって僕は「父ちゃん」という役割だが、唯一無二のその役割を5年間全うしてきたことになる。飽き性の自分からすると、よく続いたものだと思わざるを得ない。
たまに保育園(正式にはこども園)に迎えに行くと、去年ごろからおともだちの前でだけ、「パパ」と呼ぶようになった。
帰りの車の中で、
「・・・さっきのパパって何?」
「父ちゃんのこと」
「父ちゃんって呼んだらええやんか」
「いいの!」
ムクれる姿は、もういっぱしのレィディである。
使い分けているのだ。他の子が「パパ」と呼んでいる中、自分だけ「父ちゃん」で貫くのは難しいとみえる。
他人の呼び方を、周囲の状況に照らし合わし、自分がまわりから干渉されないレベルで落ち着かせようとする、娘なりの防衛策であろう。
周囲の空気を読むのは良いが、自分のオリジナリティを皆に認めさせる胆力も、時には必要だ。一般的な人生においては、もしかしたらこういう場面でも臆することなく「父ちゃん」で貫く子の方が大成するのかもしれない。
我が子だけに「必要以上に周囲の空気を読もうとする性質」が引き継がれてしまっているのかもと、少々心配になる。
再び、車の中。
「父ちゃん」
「なんや」
「帰ったら、絵本読んでや」
「分かった。何冊?」
「10冊」
「多い。母ちゃんに読んでもらえ」
「嫌や! 父ちゃん!」
「父ちゃん」と呼ぶ意味と、「パパ」と呼ぶ意味。
彼女の中では、純然たる違いがあるはずなのだ。
何の心置きもなく「父ちゃーん!」と叫び、泣きわめき、満面の笑みで笑いかけてくる。
その内、「父ちゃん」と呼ばれなくなる日がくるかもしれない。
それはそれで寂しかったり、悲しかったりするのだろうが、そんな「親の感傷」など、この娘の成長には何の関係もなく、そもそも煮ても焼いても食えない。
僕のあぐらにちょこんと座り、ライナスの毛布であるガーゼケットを持ち、僕が毎週図書館から借りてくる絵本を読み聞かせる。長年の決まりきったこのルーチンも、あと何年続くだろう。
大きくなるにつれ、あぐらに乗せ続けると足に負担がかかるようになった。またジムに行って、ふくらはぎを鍛えなくては。
「なあ、娘」
「なに、父ちゃん」
「父ちゃんの膝に、いつまでこうして乗っかるつもりや」
「うーんと、えーと。8さいまで!」
「何で?」
「8さいがええから」
「8さいがええんか」
「うん」
「じゃあ、そうしようか」
「うん」
自分のふくらはぎが、他人の役に立つなんて、一人で生きているときは考えられなかった。
あと3年、娘を軽々と支えるために、スクワットをしなければならない。