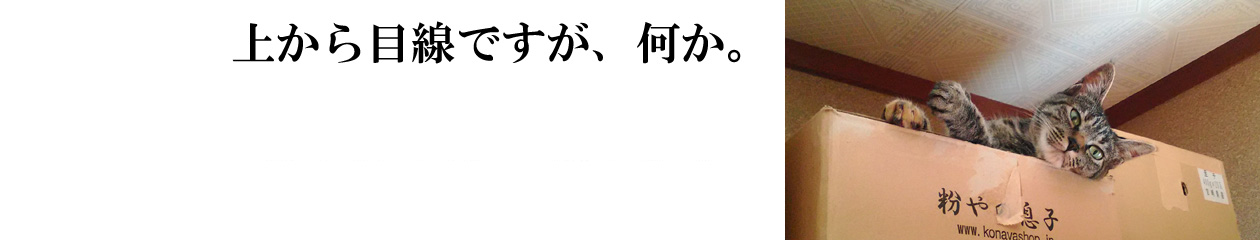去年の十一月、出張で兵庫県豊岡市へ行った。
仕事の合間の休日を使い、一人電車で城崎温泉の駅に降り立った。
特別、城崎温泉に行きたかった訳ではない。
宿で一人することもなく、かといって街に繰り出したい訳でもなく。それなら二駅先の城崎温泉にでも行こうか、ここで行かないと二度と行くチャンスはないかもしれないし、という薄軽い気持ちだった。
駅前の広場には観光客がごった返していた。外国の方も結構いた。ご時世だ。
城崎温泉の有名どころと言えば「外湯めぐり」だ。今までに二回来て、巡っているはずなのだが、ほぼほぼ記憶にない。
えーと確か、最初に来たのはかれこれ三十年前と・・・。
そんなことを考えながら、商店街を歩き始める。
有名なスマートボールの店は覚えていた。まだあったんだなと驚く。
ワイシャツとスーツしか持ってきてなかったので、そんな恰好で外湯をめぐる謎のおっさんの姿は、さぞかし観光温泉地で奇異に写っていたことだろう。
* * *
初めて城崎温泉に来たのは、十九くらいの頃だった。
右も左も分からない、高校卒業したての若造を、職場の先輩方が連れて行ってくれた。
男女混合で、十名くらいの大所帯。学生時代にどぶねずみ色の青春を送っていた僕にとって、その選抜メンバーの中にいるというだけで、勝手に大人の一員になれたような気がした。でも振り返って考えると、所詮ただの人数合わせだったんだろうと思う。
それでも僕らは、大人数で旅行にいけること自体が楽しかった。年若い何も知らない僕らは、先輩たちの後ろを金魚のフンよろしくつけまわり、一つ一つの所作を真似ては、社会の常識とやらを一つ一つ吸収していった。
記憶の奥底に眠る、そんな若い頃のことを想い出したのは、フェイスタオルを購入し、一番奥の外湯である「鴻の湯」へ行ったときのことだった。
はて、こんな遠くの外湯まで来たことあったっけ?
外湯めぐり券がQRコードになっていたことに驚きと戸惑いを隠せず、風情が云々とか便利が云々とかグルグル頭の中を巡らしながら。
すっぽんぽんになって湯船に入った。
うん、全く覚えていない。でも内湯は深めで入りやすい。露天は山の麓にあり、外気温が低いので気持ちの良い景色ではあった。
風呂上り。
湯船で体を洗うのに使用したフェイスタオルを良く洗い、再度拭いては水けを絞り、繰り返して脱衣所へ出て、そのまましばらく休憩して扇風機などにあたり体を乾かす――。
そういえば僕は、三十年前の先輩たちとの旅行で、この方法を教えてもらったのだった。教えてもらった外湯はここではなかったのだが(おそらく一の湯だったと思う)。
「外湯行くぞ」
「タオルだけで行くんですか。バスタオルはないんですか?」
「そんなもんいらん。これ一つだけでええねん」
爾来、僕はフェイスタオル一つあれば、風呂屋で何とかなるようになった。城崎温泉の外湯で、その作法を教わったのだ。
――人の「記憶」は、場所によって、呼び起される。
城崎温泉に来なければ、そんなエピソードを思い出すことはなかった。日常に埋もれ、記憶の底に沈み、日の目を浴びることはない沢山の記憶の断片。
その場所に行けば、否応なしに蘇る。
その記憶は、楽しかったり嬉しかったり、寂しかったり悲しかったりするかもしれない。
思い出すエピソードを、選ぶことはできない。
楽しい思い出を呼び起こす場所であっても。悲しい思い出を呼び起こす場所であっても。無差別に等しく思い出してしまう。
そして。僕は思い出す。
城崎温泉は僕にとって、楽しく、悲しく、そして切ない場所だったのだということを。
* * *
外湯を出て、駅の方向へ戻る。
「まんだら湯」は休みだった。出ている看板が読めないのか、外国人観光客が入ろうとしている。英語が分からないので、とりあえず見なかったことにして後にする。
「御所の湯」は、豪勢な風呂場だった。露天に滝が落ちており、すごい迫力である。観光客には受けそうだ。
「柳の湯」は、時間的に入れなかった。
「一の湯」は、脱衣所にかすかな記憶が残るが、湯船にどうも記憶がない。
――どこだったんだろう。
おぼろげに思い出した記憶の中の風景を、外湯をめぐりながら探していた。今日これまでに入ってきた外湯では、なかったはずだった。
二回目に、城崎温泉へ来た時。
その日は大雪だった。僕はすっぽんぽんになり、平日で誰もいない露天風呂に飛び込んだ。
次々と、漆黒の闇夜から間断なく降り注ぐ、白い雪。温泉の水面に落ちては、一瞬で溶けて消えた。
一生の内でそうそう見ることができない景色に同化しながら、僕はいつまでも降りしきる雪を眺めていた。いつまでたっても、湯冷めもしなかったからだ。
外湯を出て、脱衣所で服を着る。
暖簾をくぐり、玄関先の椅子を見る。座って待っていた彼女が振り向き、手を振る。僕は彼女に、「すごかったね」と告げた。
「うん。すごかったね」
降りしきる雪の景色ともに。その時僕に見せた彼女の笑顔もまた、一緒に思い出したので。
少し、胸が苦しくなった。
僕が二回目に城崎温泉へ来たのは、二十三歳の頃。
大学生の頃、当時つきあっていた女の子と訪れた。
彼女は、宇治のええとこの娘さんだった。二歳年下の彼女は、何かにつけて若かった。
文学部の授業の、その年の課題が志賀直哉だったことから、
「志賀直哉を研究するんやったら、城崎温泉やろ。冬休みに一泊旅行いかへん?」
そうやって下心丸出しで僕が誘ったのか。それとも実は彼女の方からそうやって誘ってくれたのか。
もう思い出せない。けど、きっかけは志賀直哉だったことに間違いない。文学館の前ですまし顔をしている僕の写真が、実家に残っているのだ。
電車を乗り継ぎ、二人で城崎温泉へ来た。この電車はいつまでも、止まらず走り続けるものと信じて疑わなかった。
彼女は家族に、女友達との旅行だと嘘をついて来てくれた。
「城崎温泉に行くんだったら、家族旅行でよく使う旅館があるの。まかせてよ」
彼女が予約を取ってくれたのだが、今思うと家族が良く使う宿には泊まったらあかんかったんちゃうかいと思わなくもない。
当時の彼女は、「私だって、できることは沢山あるんだから」というアピールを、ことあるごとに僕にしていた。
何も知らない。何も分かっていなかった当時の僕と。
彼女もまた、恋に恋しているような、どこにでもいるような普通の女の子だった。
* * *
「地蔵湯」に入って、外に出た。
川の両脇には、枝垂れ柳が植えられている。
後は駅前の「さとの湯」だけだ。だがあそこはスーパー銭湯然としていて、風呂が階段を上がった二階にあるらしい。さすがにそこではないと分かっていた。
結局その日は、当時の彼女と一緒に見た大雪の露天風呂が、どの外湯だったのか分からなかった。
臨時休業の外湯と、昼から開店する外湯があったので、もしかしたらそこだったのかもしれない。しかし時間的に、そろそろ宿に帰らないといけなかった。
城崎温泉へ来ることは、もうないかもしれない。
分からずじまいになるけれど、それはそれで良かったかもしれないと思った。
彼女の思い出は、今の僕には必要のないものだ。忘れていた物であり、忘れようとしていた物でもあった。
お店でコロッケを買ってパクつく。その先の角を右に曲がって、文芸館通りを歩き、城崎文芸館に来た。当時の僕がすまし顔をして、彼女に写真撮影してもらった時の場所だ。
「せっかくだし、誰かに一緒に撮ってもらおうよ」
僕が言っても、写真を撮られることが大嫌いだった彼女は、頑として首を縦に振らなかった。
なので当時の旅行の写真に、彼女は一枚も写っていない。写っていない写真はやがて年月を経て、彼女自身の記憶をも溶け込ませてしまっていた。
だから呑気にも、ノコノコと忘却の地に、足を踏み入れてしまったのだろう。
そういえば当時。
宿泊する旅館に入る前、彼女が僕に言った。
「ねえ。お願いがあるんやけど」
「何?」
「宿帳って書くやん? あれにね、同じ名字で書いて欲しいの」
「別にいいよ。それくらいなら」
宿の受付へ行き、大阪の実家の住所を書く。そこに僕の名前と、名字を僕のものにして、横に彼女の名前を書いた。
振り向いたとき、彼女は照れくさそうな、それでいて嬉しそうな顔をしていた。
「現実になればいいね」
嬉しそうに、彼女は頷いた。
しかし僕は、宿帳の彼女の名前を、現実にしてあげることはできなかった。
それどころか、彼女に一生の傷を負わせるほどの酷いことをしてしまい、最終的に彼女は僕の元から去って行った。
* * *
そろそろ宿に帰らないと、夜の作業に差し支える。
まだまだ観光客の姿は残っているけれど。
僕は一人、ホームに入ってきた電車に乗り、城崎温泉駅を後にした。
列車がゆっくり走り出す。車窓には、収穫を終えた田んぼの風景が広がる。ぼんやりと、窓外を眺めながら物思いにふける。
永遠の愛が、「ない」とは言わないけれど。
それは細く脆く、果てしなく困難な道だと、おっさんになった僕は思っている。
「絶対に一生守ってあげる」だとか。
「絶対に一生好きでいる」だとか。
「嫌いになんて、絶対にならない」だとか。
歯の浮くような青臭いセリフを言っていた頃の、当時の僕を思い出す。
(最低な奴やったな・・・こんなこと想い出したくて、城崎まで来た訳やなかったんやけど)
そんなことを考えながらも、今の僕と当時の僕と、そんなに変化ないことも、よく分かっている。人間、そんなにコロコロ変われるものでもない。
「世の中に絶対なんてない」、と巷間ではよく言われる。
ならば、当時の僕が彼女に言った言葉は、嘘だったのだろうか。
少なくとも、当時の僕はウソ偽りなく、本気で思っていただろう。
一生、守りたかったのだろう。
一生、好きでいたかったのだろう。
結果的に、叶えることができなかったからといって、その時の感情までを否定しなくても、良いのではないか。正当化したい訳でもなく。何もそこまで。
記憶を封じてまで、当時の自分を卑下しなくても、良かったのかもしれない。そう思った。
記憶に封をするのではなく、当時の自分と向き合って、腹を割って話し合っても良いのではないか。それが例え、現実味のなかった、青臭い夢語りの記憶だったとしても。
彼女は大学を卒業してすぐ結婚し、子供も生まれたと聞いた。
良かったと、思うのと同時に、胸のどこかがチクリと痛んだ。
結婚式に参加した同級生から、話を聞いた。
「アンタには会いたくないけど、アンタのお母さんには良くしてもらったから会いたいって。笑って言ってたよ」
彼女らしいコメントだなと思い、僕は少し笑った。