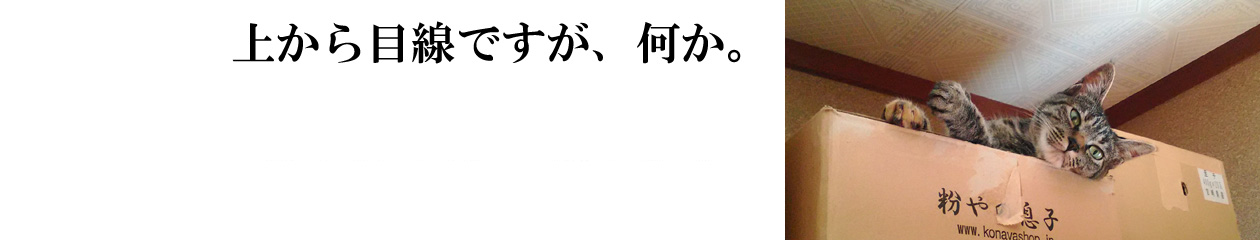パソコンの奥底に眠っていた、昔書いた文章を一人、夜に読んでみた。
* * *
「――ある夏の夜にね」
「はいはい」
「午前一時半くらいかな。窓から『シャー』という音が聞こえてきてん。『わー』とか『きゃー』とか、響きわたる歓声とともに」
「なんでしょうね」
「俺の部屋って、窓の外道路に面してて、向かいにガレージがあるんやけどな。網戸ごしにのぞくと、そこでカップル二組が花火してた」
「夜中の1時半に花火ですか?」
「閑静な住宅街の一角のガレージでね」
「閑静かどうかは疑問ですけど」
「平日やし、夏休みでもなし。大抵の人々は寝てただろう」
「ちょっと非常識ですね」
「多分そいつらの常識では、午前1時半の花火は許容範囲内なんやろな。しばらく待っても近所のどなたも注意しないみたいなんで、『どれどれ、俺もええ年齢になったことやし、ここらでひとつティーンエイジャーを怒鳴って軽く嫌われてみようかな』と思って」
「変な志だな、おい」
「窓をガバッと開けて。『こら、お前ら今何時や思とんねん』と叫びたいところをグッと抑えて」
「なぜ抑える」
「『静かにせぇ』と一言。そして速攻で顔を戻して窓閉めたという伝説が今ここに」
「効き目ないでしょうが。それじゃ」
「そうは言うけど。聞こえるか聞こえないかの微妙な声量を搾り出すのに、どれだけ俺が苦労したか」
「苦労の方向性が間違ってるよ!」
「しゃあないやろ!俺の血統は小市民なんやから。ほどなくして花火も終わったようで静かになって。小腹すいたんでコンビニに行こうと外に出たら、ガレージに大量の花火の燃えカスが残ってました」
「愚か者の集団ですな」
「そこに向こうの暗闇の中から、『ゴーロゴロゴロォォォ』という音を響かせ、スケボーに乗った若者がやってきた」
「・・・」
「ところで昔、『ニュースステーション』で久米宏が、『僕は夜中の1時とか2時頃によく散歩するんですけど』って言ったのよ。それを受けて、当時アシスタントやった渡辺真理が『夜中に散歩ですか!?』ってつっ込んでたのね」
「夜中に散歩って、コンビニか何か」
「いや、一時間くらい街中をねり歩くんだって」
「職務質問受けませんかね」
「昔やったらな。今はコンビニとかラーメン屋とか、その時間でも開いてるところ多いし。闊歩してる輩も結構おるやろ」
「そういやそうかな。でも一時間も夜中に散歩なんて、女性にはできないでしょ。だから渡辺真理も驚いたんですよ」
「そうやねんな。でも俺、久米宏の気持ち分かるねん。俺もたまに夜中散歩するから」
「ああ、あの三丁目の橋に出没する痴漢は、あなただったのですね」
「おい、失礼やな! 誤解招くようなこと言うな!」
「すいません」
「一丁目や」
「そっちかい」
「冗談は置いといて。俺らの利用してる駅て、夜中の最終とかひとつ手前の駅で止まってまうやん。そういうとき、タクシーはもったいないから、歩いて帰るときあるやん。そうなると、必然的に夜の街を闊歩せなアカンやろ」
「隣の駅、かなり離れてるしね」
「だいたい徒歩40分くらいかかるかな。俺はよく歩いて帰ってたな。ほら、よく『歩くと頭の回転が良くなる』って言うやん」
「言いますね」
「それは俺、ホンマやと思うな。昔の人は当然のことながらよく歩いたそうやけど、『たけくらべ』の樋口一葉なんかは、一日三十キロぐらい歩いたらしい」
「へー」
「女の人でもそれぐらい歩いてた。車もバスもないからね。漱石とかの小説にも、よく散歩の描写がある。散歩で物思いに耽るわけだから、昔の人は妄想する時間が腐るほどあったってワケやな。そら小説のネタもボコボコ浮かぼうってもんだ」
「京都には『哲学の道』がありますね」
「昔の京都の書生さんは、よくあそこを歩いてたらしい。悩みながら。現代の学生は部屋で悩むから、頭回転せぇへんし、しんどい面もあるんちゃうかしら」
「しかし、それと夜の散歩とどう関係があるんですか?」
「昔はね。場所によっては、昼間でもそんなにうるさくなかったと思うんだな。時折聞こえてくる雑音も、かえって静けさを増すような。今、都会でそういう状況は、夜の散歩でしか手に入らないんだよ」
「ああ。なるほど」
「夜歩いてるとな。夜には、『夜の音』があることがわかる」
「・・・」
「そんな、『とうとうやっちゃったよコノヒト』みたいな目で見るな。今から説明する」
「カエルの鳴き声とかですか?」
「それもあるけど。寒い日とかやったら、空気が緊張する『キーン』とかいう音とか聞こえたりする」
「ああ。それはなんとなく分かる気がするな」
「そういう状態は、集中力あるときやけどな。だから、静かじゃないと聞こえない。矛盾した音だ。夜歩いてると聞こえてくるのは、自動販売機のモーター音とか、夜風の切れる音とか、たまに走ってくるタクシーの音とか」
「虫の声とかね」
「そいつらは昼間も鳴ってるんやろうけど、いろんな『昼の音』に消されて聞こえない。みんなが寝て静かになると、そういう音が聞こえてくる。夜の静けさが際だつ。それが『夜の音』」
「って言うんですか?」
「いや。俺が勝手に決めてるんやけどな。悩み事とか、考え事とか、頭の中で転がすには静かな場所で歩いた方がいいんだろうと思うんだ。人間が目をつぶって考え事するのは、画像データが一番情報量大きいからや。夜は黒一色やから、脳味噌の処理能力が、悩み事を処理する方にまわせるんじゃないのか」
「ほんとですか?」
「コンピュータでも、一番データ量が大きいのは、グラフィックとサウンドやんか。人間は昼日中、目を開けて耳を傾けて膨大な情報量が入ってくるから脳が疲れる。だから脳を休ませなアカンのです」
「じゃあ、夜中に散歩してる場合でもないでしょう。早く寝なきゃ」
「それを言っちゃあ・・・」
「最初の話はどうなったんですか」
「小腹がすいてコンビニに歩き出した俺は、歩きながら考えたんですよ。『常識』ってあるやんか。あの若者どもは、夜中に騒いだことが常識外れな行動なワケで」
「そうですね。スケボーに乗ってたにいちゃんは、夜中にうるさいスケボーに乗ってたから常識外れと言われるワケで」
「でもさ。スケボーのにいちゃん、片手にコンビニ袋もっててん。どうも、俺の行こうとしてたコンビニからの、帰りやったらしい。移動手段やったわけやね」
「でもやっぱし非常識ですよ。警察がいても注意するでしょうし」
「ほなこれが、スクーターやったらどうなの? 『うるさいなあ』とは思うかもしれないけど、『非常識だ』とは思わんのとちゃうかな。車でも」
「うーん、そりゃそうでしょうが」
「良いか悪いかは、この際横に置いてくれ。こういったことは『常識がない』の一言で済ませてしまえることなんやけど、それは一番簡単に言えるんやけど、簡単なだけに一番真実から離れてるのではないだろうか。そう思ったのだ」
「はあ」
「『常識』ってのは、言ってみればただの『箱』や。みんな全く同じ、『常識って名札の付いた箱』を持ってる。でも、箱の中には、それぞれ微妙に違うものが入っている。年齢によって違う。家庭でも違う。学校によって違う。国によって違う。それこそ隣の町でも違う。今まで読んできた本によっても違う。つきあってきた友達とか恋人によっても違う。育った土地と水や空気によっても違う。何から何まで、微妙にずれてる」
「まあそうでしょうね」
「そして、『違うことが当たり前』やのに、みんな同じやと思っている。箱だけしか見ない。同じやないと嫌なんやな。というか、同じやないと不安なんやろう」
「まあね」
「中身は違うのに、それを入れる『箱』はみんな同じ形をしてる。『常識』と書かれたシールが張ってるだけやのに。だからみんな、無意識に『みんなと中身も同じやろ』と思いこむ。だから他人が突飛な行動をとると『あいつは、俺の箱の中身と違うことをしている。だからあいつは非常識だ』と決めちゃう。親は子を決め付ける。子は親を決め付ける。生徒が先生を決め付ける。先生が生徒を決め付ける。他人が自分を決め付ける。そして…自分が他人を決め付ける」
「決めちゃう方が楽ですからね」
「『常識』っていうのは法律やないから。六法全書みたいに書き記されてるわけでもなし、絶対の型はないやん。生きてる時代時代で、生きてる人間どもが暗黙の了解で作りあげたもんや。でもそれは、完成することはない。でも、完成してると思いがちやねんな」
「僕らも含めてね。なるほど。だから、花火してたやつらもスケボーにのってたやつらも、一概に『常識外れ』とは言えないと」
「常識外れには違いないんやけどね」
「どっちやねん!」
「まあでも、『アイツは常識がない!』と怒ってしまうのは、一種の自己防衛なんやないかと思うのですよ。自分の持っている、『常識』という箱を守るための。それは、昔は結構有効やったんやろうけど、今はもう無効になった」
「ふーん」
「そういう意味では、『夜は静かに!』っていう常識も、世の流れ次第ではなくなるのかなあと思ってね」
「夜更かし人口増えてるしね」
「『祭囃子が遠くに聞こえる』って言葉があるやないの。お祭りってのは先祖代々、社会的に夜騒いでも許されるイベントなわけですよ。それ以外のエリアは静かな夜だから、遠くのお囃子でもこっちまで聞こえてくる。でもこの社会はそのうち」
「全員が夜に騒ぐから、『祭り囃子が遠くに聞こえない』社会になると」
「夜の常識が変わってしまえば、昔の小説を読んでそんな言葉が出てきたたとしても、実感もわかなくなるときがくるのかな、と思うわけです。それがね、何だかとても悲しいことのように思えるんだ」
* * *
昔書かれた文章は、今読むと、現在の自分には書けないような思いや情熱が溢れている。
今の僕には、とうてい書けない文章だ。それが恥ずかしくもあり、懐かしくもあり。羨ましくもある。
当時の僕は、「夜の音」に、色々な意味を込めようとしていた。でも今読むと、少し理に走っていておしつけがましく、何となく言いたかったことが書ききれてないように思った。
年を経て、僕は夜の町を闊歩することはなくなった。それはきっと、その頃は聞こえていたはずの「夜の音」が、聞こえなくなってきたからだ。
今の僕に、「夜の音」は聞こえない。
読んでいる途中で、本を買い忘れていることを思い出した。一時まで開いている駅前の本屋まで、買いに行こうと思った。時刻は十二時半過ぎ。文章の中の、昔の僕がコンビニに行ったのと、だいたい似たような時刻だ。
家を出る。
家の窓からこぼれる明かりは、まだまだ多い。盆も近い夏の夜。クーラーの室外機が、各家庭でうなっている。
テレビの音がこぼれている。どこかで男たちの笑い声が、響いている。住宅街の交差点の真ん中で、高校生らしい集団が、自転車にのりながら話をしていた。通り過ぎるときに、数人がこちらを見た。
大通りに出る。
コンビニの前は沢山の人だかり。駐車場にも、沢山の車が止まっている。暑いからだろうか、エンジンを切っていない。大通りは、タクシーだけでなく、普通に沢山の車が走り抜けている。
若い女の子が、駅の方から携帯電話で話しながら帰ってくる姿を、あちこちで見かける。夜の道に、相手のいない独り言が飛び交っている。
背広姿の男と女が、酔っ払いながら自転車屋の前で、自転車のタイヤに空気を入れている。酔っているから男の声がでかい。負けずと女の声もでかい。フラフラしながら、二人乗りで帰っていく。
赤い点滅信号を一時停止しなかった車に、対向車がクラクションを鳴らしている。点滅信号は深夜のシンボルだけど、交通量は深夜の道路に見えない。マフラーを改造したバイクが、大きな音を立てて走っていく。
駅前に近付く。
朝まで開いてるチェーン店の居酒屋、カラオケボックス、定食屋がたくさんできたせいで、街は明るく闇を照らす。電車がなくなっても沢山人がいる。酔っ払ったサラリーマンの集団が、大声で笑いながら道を歩いている。そのサラリーマンに、呼び子が声をかけている。
沢山の人の話し声が、沢山耳に入ってくる。
駅前の本屋に入る。
本屋の中は明るいけれど、閉店間際で人はまばらで、店内には有線放送が流れている。
その内、店内に蛍の光が流れてきて、急いで目的の本を買い、外に出る。
なんとなく、来た道を歩きたくない気がして、別の道から帰ることにする。
24時間営業のスーパーが近所にできたので、もう一つの道も沢山の人で溢れている。店の中から、繰り返しスーパーの名前を連呼したアナウンスがもれてくる。
スーパー近くのコンビニで。ママチャリの荷台のシートに、一人の男の子が座らされている。その目が、コンビニの中をじっと見ている。
母親とおぼしき女性が、カゴを片手に携帯電話を片手に、コンビニの中を歩き回っている。その姿を、荷台から下ろされる事を許されず、子供がじっと見ている。
僕はそれを見ながら、少したたずむ。そして思う。やはり僕には、もう「夜の音」が聞こえない。
良いことか悪いことかは分からないけれど、僕にはそれは、昔書いた文章のように、悲しかった。
たった数年で街は変わり、僕も変わった。今僕がいるのは、夜という名札を首からぶら下げているだけの街だ。
さっきの小さな子供は、静かな夜を知っているだろうか。夜の音を聞いたことはあるだろうか。
夜の音が聞こえない社会で、夜の音が聞こえない僕らの作ったこの街で。誰にも起こされることなく、毎日眠れているだろうか。
なんとなく、電柱の広告を見るフリをしながら、コンビニから母親が出てくるのを確認してから――。
僕はまた、夜の街を歩き出す。