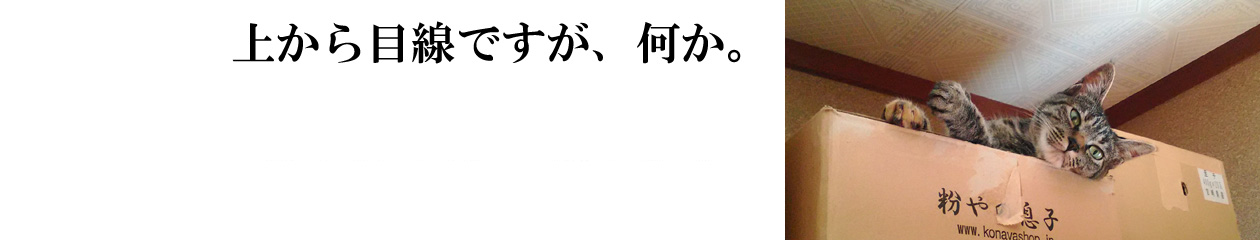死の間際。
息絶え絶えに伸ばした、母の「てのひら」は、息子である僕ではなく、父に向いていた。
「あんたはもうええからどいて」
母は僕にそう叫んだ。
「お父さん。手ぇ」
気の弱い父は目を見開き、病気のせいで動かなくなってしまった母の「てのひら」を、必死に強く両手で握りしめていた。
しばらくして。苦しんで苦しんで、母は逝った。
母の果てしなく長く続いた闘病生活は、そうして終わりを告げた。
* * *
あれからもうすぐ、二十年が経とうとしている。
それからの僕は、苦しいときや悲しいとき、頭が狂いそうになった時など。
心が「もうだめだ」と叫びそうになったとき。
自分の「てのひら」を、ただひたすら見つめ続けることが、癖になった。
「この人間を切ろうか。もう少し我慢して、繋ぎとめるのか」
自問自答しては、苦しみぬいた母の死に際を思い出し、「てのひら」をひらいたり、閉じたりしては、自分自身に、こう問いかける。
――お前の「てのひら」は。
掴むためのものか。
放すためのものか。
何度も何度も、問いかける。
* * *
僕の母親は、「強皮症」という病気で死んだ。
正式名称を、「全身性強皮症」という。
手の皮膚が、カチコチに固くなる病気だ。そして皮膚の硬度のせいで、指が曲がらなくなる。
膠原病という分類に入る。現在では免疫疾患の病気であることが分かってきているが、当時は今ほど情報もなかった。
現在は、様々な薬が開発され、進行を遅らせることができる。QOLも当時よりは向上している。診てくれる病院も増えた。
その頃は、決して完治せず、対症療法しかなく、疾患は徐々に全身に広がり、やがて命を奪う病気だった。
家族の行く末だけは、どの医者もはっきりと教えてくれた。
沢山の病院に入院しては、手の施しようがないという医師からの回答を受け、失望し退院しては部屋に引き込こもる。
母は荒れた。家庭の雰囲気は徐々に悪化した。健常者である僕らへの、罵詈雑言が増えた。
その後、我に返った母の謝罪の言葉を「仕方ないよ」とあやし、日々を暮らしていく。
その繰り返しはとても辛く、憤りや不満をヘドロのように少しずつ溜め込み、「家族」という形式を維持することに、それぞれが疲弊しきっていた。
時に母は、極度の食事療法にも手を染めた。
修行のような食事療法の末。病気が進行しており、母の腸はほとんど食物を消化する能力をなくしてしまった。
しかし人間の脳はその生存本能から、飢餓状態を続けると一転過食状態に陥る。
頭から食べ物のことが離れない。食べたくて仕方ない。
しかし消化することができない。
度々、飢餓に飢えた脳の命令に抗うことができなくなり、自室のベッドに大量の食料を持ち込んでは、夜中に泣きながら嘔吐していた。
僕は、夜中のトイレに起きだすふりをしては母の部屋をのぞき、見つけては黙って背中をさすっていた。
「ありがとう。食べたらあかんのに、またどうしても食べたなってな。情けないお母ちゃんやんな」
言葉が無力だということを、反吐が出るほど知った。
慰めることも正解ではない。
怒ることも正解ではない。
責めることも正解ではない。
何が正解なのだろう。どうすれば、母は癒えるのだろう。
誰も悪くない。誰も間違っていない。
何もおかしくはない。
ただ、苦しんでいる人がそこで泣いているだけだ。
言葉は無力だ。何も癒せず、何も解決することができない。
若かった僕は、誰かに正解を教えて欲しいと願いながら、ただ黙ってひたすらに、自分の「てのひら」で、母の背中をさすり続けた。
さすれば母が癒されると思っていた訳ではなく、それしか、やることがなかっただけだった。
* * *
手足だけでなく、母の腸の細胞も病で硬化していたため、ほとんど動かなくなっていた。
そこに食料が入ってきたらどうなるか。
腸に便が詰まって、母は目を見開いて苦しみながら、僕と父の目の前で息絶えた。
定年退職後、毎日休まず見舞いに来てくれる父に向かい、母はこれまた毎日休まず罵詈雑言を吐いていた。
「見舞いに来ること以外、やることないんか」
「あんたなんかと結婚せんかったら良かった」
「私の手がこんなんになったんは、家事を全く手伝わなかったアンタのせいや」
寡黙な父は、そんな身勝手な母の罵詈雑言にも怒らず、黙って聞いて、話もせずにテレビを観て病室で一日過ごしていた。
母は父に、感謝の言葉一つかけなかった。
僕は母の気性を受け継いだ息子だったので、母に気に入られていると思っていた。母親のことを誰よりも理解していると思っていた。必要とされていると思っていた。
だが、死の間際に母が伸ばした「てのひら」の先は僕ではなく、日々罵詈雑言を浴びせ続けた、父の方だった。
母は、父にしっかり「てのひら」を握りしめられながら、死んだ。
今なら分かる。
母の死に際は、苦しかったかもしれないけれど、満たされたものだった。
病気のせいで、自分からはもう握れなくなっていた「てのひら」を、握りしめて欲しい人が傍にいて。
強く握りしめられながら、ぬくもりを感じながら死ねる人が、この世に何人いるだろう。
罵詈雑言を受けながらも父は、必死に母の「てのひら」を握っていた。
決して、離すことはなかった。
母は父に感謝の言葉を伝えなかったが、握りしめられた母の「てのひら」は、言葉以上のものを、父に伝えていた。
僕の両親は、お金持ちでもなく、才能に秀でたわけでもない。自分勝手で怒りっぽい母親だったし、自己主張のない冴えない父親だし、総じて平凡な両親だったけど。
僕は、この二人の子供で良かったと、その時素直に思えた。
* * *
生きていると、色々あると思うよ。実際、色々あるしな。
裏切られることもある。失望することもあるだろう。
逆で、裏切ることもあるよね。失望させることも、無論あるだろう。
他人との関係を、断ち切りたいと思うことも、当然あるよ。
人間だからな。
そういうとき僕は、「てのひら」を、何も考えないで、見つめてみる。そうすると、もう一人の自分が、語り掛けてくるんだ。
――お前の「てのひら」は。
何かを、掴むためのものか。
何かを、手放すためのものか。
頭がいかれても、吐きそうになっても、泣きながらでも。そのまま死んだっていいけれど。
「てのひら」は、大切なものを握りしめるために、あると思うんだよ。