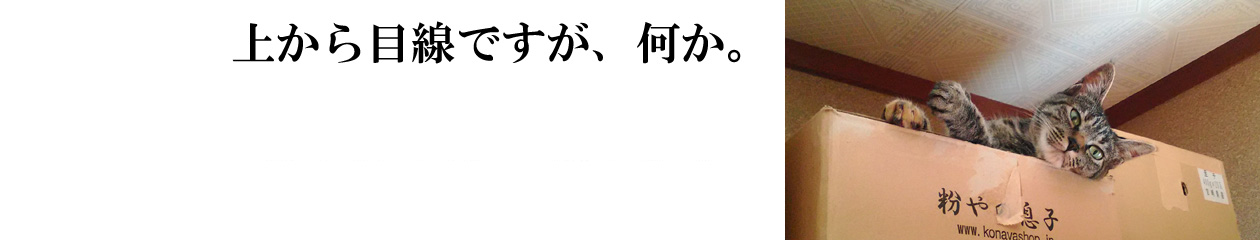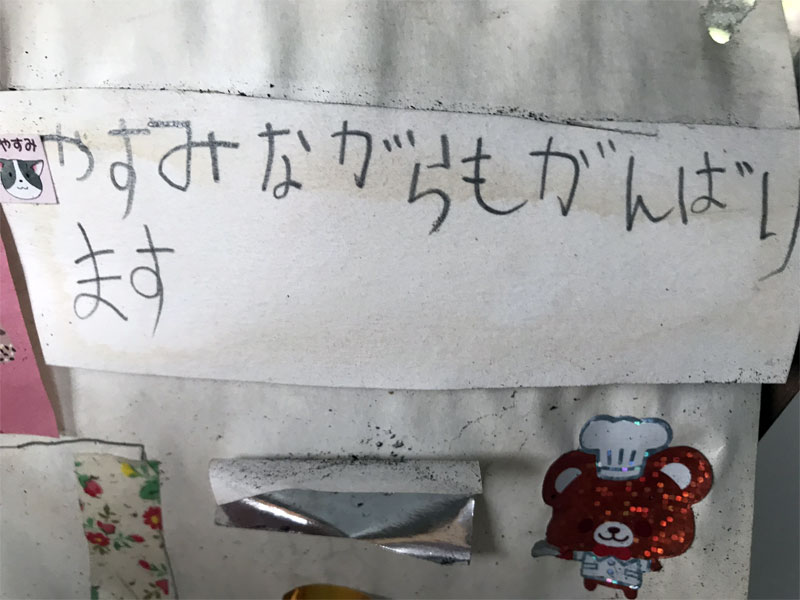介護の話を、少し書いておきたい。
左手左足が動かなくなったにもかかわらず「病院に行きたくない」と駄々をこねる81歳の老人(父)を、タクシーに乗せて脳神経外科へ連れて行き、診てもらった医者に「即入院」と宣告されたのは、2017年の11月初旬。あれから四年が過ぎた。
紆余曲折経て、父は某所の老人介護施設に身を寄せている。コロナ禍で長期間面会することはできていないが、「今は」静かに暮らせているらしい。この施設も色々問題が多いのだが、父がストレスなく過ごせているようなので我慢している。不満を全部書くと冗談みたいな話になってしまうので、とりあえず書かないでおく。
父は、タイミングが悪い。
毎回タイミングが悪いという訳ではないが、「ここぞ」というタイミングで禍事が起きる。なので印象がとても悪い。サッカーでも「ここぞ」というところでゴールを決めるのがエースストライカーだ。野球でも負けることができない試合を任され、ナイスピッチングをする投手をエースと呼ぶ。父も似たようなものだ(そうか?)
周囲の人間(主に僕)をピンポイントに狙い、最悪のタイミングで何かを起こす。ただ「最悪だ」と思っているのは、父の出来事に巻き込まれている肉親の僕だけだ。なので周囲には、なかなか同意してもらえない。
もちろん、父はわざとそうしている訳ではない。父は父とて生き、父として生活した結果、そうなっている。本人からすれば「逆恨み」だ。関係ない人から見れば「言いがかり」。なのでこれは、僕の「愚痴」である。
父は、タイミングが悪い。
父が脳梗塞で入院した日、奥さんに電話で告げると、義父も末期がんが発覚して入院すると言われた。自分が仕事の時に、病院に着替えを持っていくなどの父の用事を、奥さんに頼めなくなってしまった。向こうはこちらより、命に係わる事案のパーセンテージが高い。父の事での相談も、しにくくなった。
前にも書いたが、長兄は先月中国へ旅立ったばかりだった。二年間滞在予定の単身赴任。それも伸びに伸びてやっと出発したところだった。同じく父の用事を任せることもできず、相談もできず、自分一人で判断しなくてはならなくなった。
前にも書いたが、母はとっくに鬼籍に入っている。
父の面倒や病院との対応、今後の医療判断、介護の方向性など、見事にピンポイントで自分一人に集中した。一カ月前だと、兄もいるし奥さんも余裕があるので、こうはいかない。父の嫌がらせとしか思えない。「逆恨み」かつ「言いがかり」かつ「愚痴」である。
父は、タイミングが悪い。
施設から僕のスマホに着信があったのは、今年の五月のGWの夜。徹夜の仕事へ向かう電車内での事だった。いけないことだが電車内で小声で電話に出た。途中の駅で降りると次の電車がなくて仕事に遅刻してしまう。何より乗っている電車は特急なので途中駅にしばらく止まれない。あと一時間前にかかってくればいいのに、とまず施設を呪う。
「お父さんが施設で転倒し、股関節が痛いとおっしゃっています。救急車を呼ぶのですが、このご時世なのですぐに診てもらえるか分かりません。今から来れますか」
という内容だった。色々重なり過ぎていて眩暈がした。
時はコロナ禍、市中がデルタ株に置き換わりつつあり、夏に向けて感染者数が全国的に激増していた。重症者数も増え、病院への入院も断られるケースが目立ち始めていた最中。コロナ患者が救急車運送すらも断られたというニュースが珍しくなくなりつつある頃。
そんな最悪の時期に、脳梗塞の老人が転倒して救急運搬?
よりによって、一年に何回かしかない徹夜仕事の直前に?
よりによって、特急に乗ったすぐ後にかかってくる?
結果として、父は市民病院に受け入れられ、入院して手術も行うことができた。病院への付き添いは奥さんがしてくれたので、僕は仕事へ行くことができた。だが仕事先で同僚がトラブルを起こし関係ないのに巻き込まれた。GW中、都合四日間働いた現場で、同僚がトラブルを起こしたのはその日だけだった。翌日、「お父さん、大変だったそうですね。そんな時に迷惑をかけて申し訳ありませんでした」と謝られたが、僕は混乱してもうどこの誰をどう恨めば良いのか分からなくなっていた。上手に人を「恨む」ことができなくなってきたと感じる。
ちなみに父は、高齢者かつ脳梗塞というハイリスク疾患持ちなので、施設で真っ先に新型コロナワクチンを接種することになっていた。僕があらかじめ施設で接種できるよう、関係各所へ問い合わせ、手はずは整えていた。準備万端。そして接種二週間前、施設で転倒して入院となった父は、新型コロナワクチンを接種できなくなった。
世は、ワクチンが不足して供給停止となる問題が起きていた頃。入院先の病院で頼み込んだが、市民病院なので市民優先、入院患者には打てませんと断られた。
施設で転倒するのが、もう二週間遅ければ。せめてワクチン接種さえできていれば。入院先の病院でクラスターが発生したらどうしようか。そんな不安も幾分和らいでいただろうに。
コロナ禍で入院患者と面会することはできない。父と話すことや、父の病状を確認することもできない。いつ退院できそうなのか、退院したいのか。リハビリ病院に転院するのか、施設に戻りたいのか。父の「本当の」意思確認をすることができない。医者の言葉は全部を鵜呑みにすることはできない。すべて、自分の「勘」で、判断しなくてはならなかった。
本当に、タイミングの悪い人だ。
ワクチン接種することも良く分かっておらず、ただ股関節が痛いと訴え、自分は不幸だと落ち込んでいた父。自分が「タイミングが悪い」人間だとは、全く思っていないだろう。
普通に施設で生活して転倒し股関節を骨折したのが、たまたま新型コロナワクチン接種日の二週間前だっただけだ。コロナ感染者数が激増して救急搬送しにくい時期だっただけ、息子が仕事に行く直前で特急に乗った直後だっただけ。転倒した当日に同僚が問題を起こして迷惑を被っただけの話だ。父本人は、何とも思っていない。
なので、介護者の「逆恨み」と「言いがかり」と「愚痴」には、真実が込められていると、僕は思う。
退院後、父は施設に戻った。体重が10キロ落ちていたそうだ。
施設から病院へ搬送され、戻ってこれたので、10キロ体重が落ちていただとか、元気がないだとか体力が落ちているだとか、職員さんには分かるのだ。全くの新しい施設だと、比較できないので分からなかったかもしれない。
だから、引っ込み思案で人見知りで、それなのに頑固という面倒くさい父でも、施設で静かに過ごせているのだろう。
タイミングは悪いけど、悪運は強い。
これもまた、本人はそう思っていないのだろうけど。