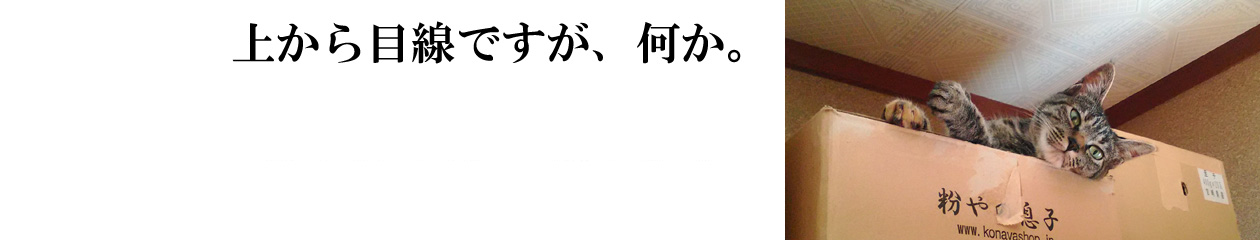隣の市に、「カツ丼が美味い店がある」という噂を聞いたので、ちょっと行ってみた。
持論を展開してみようと思う。
カツ丼を出す店というのは、大別して二種類あるように思う。曰く、「とんかつ屋の出すカツ丼」と、「うどん屋そば屋が出すカツ丼」である。
どちらの店でもカツ丼がメニューに載っていることは多いが、とんかつ屋は「丼部分が専門外」で、うどん屋そば屋は「カツの部分が専門外」だ。
そのためなのかどうだか知らないが、世の大抵のカツ丼は、なんだか中途半端な味のものが多いように感じる(多少個人の好みも反映されるとは思うが)。
昔から贔屓にしていた食堂のカツ丼が好みで、「カツ丼食べたいな」と思った時によく利用していた。しかしある時、おじさんとおばさんが高齢を理由に閉店してしまった。それを境に、自分の中では「美味しいカツ丼を食べられる店」を探すことは、死活問題と化したのであった。
ここ数年、「カツ丼食べたい」と思っては、目についた店に入ることを繰り返し、その度に敗北感に打ちひしがれて店を出る――そんな作業を一人、繰り返してきた。
チェーン店に入ってカツ丼を注文し、どす黒いカツを見て「どこまで煮込んでるんだよ」と突っ込みを入れたくなるモノが出てきて、絶望の淵に叩き落されたりもした。
今度の店もダメだったら、もう「美味しいカツ丼の店を探すなんてやめよう」と思っていたほど、事態は深刻であった(大げさである)。
話は最初に戻る。
先のカツ丼屋さんは、店主と奥さんの二人で切り盛りしている、とんかつ屋さんだった。
「カツ丼、大盛りください」と頼むと、少し無愛想な奥さんが「はい」と答え、厨房に消えていった。
所在がないので、なんとなくメニューをながめながら待っていると、厨房からカツをあげているジューという音が聞こえてきた。「ちゃんとカツあげてる。良かった」と胸をなでおろす。
チェーン店などで顕著だが、カツ部分を冷凍のもので済ませたり、あげ置きを電子レンジで暖めてそのまま利用するところもある。そういうものを食べるたび、虚しさと悲しさと心細さを感じる(愛しさと切なさと心強さは感じない)。
出てきたカツ丼は、さすがとんかつ屋の作るカツだけあって肉厚で、一口かじるとジューシーで柔らかく、衣もサクフワで脂っこくなく、申し分ない。そこにかかる玉子は白身と黄身を混ぜすぎることなく半熟で、これまた申し分ない。ご飯も確かに大盛りで、汁が多すぎることもなく少なすぎることもなく、当然申し分ない。
満足だった。申し分ないカツ丼だった。これで、大盛りでも普通でも600円(とんかつ屋はだいたいご飯おかわり自由だからかと思われる)。
世の中捨てたもんじゃねぇなおい、と思った。
* * *
マクドナルドのハンバーガーだとか吉野家とか松屋の牛丼だとかどこぞのチェーン店のラーメンだとかコンビニの弁当だとかカップラーメンだとか。
口に運ぶ日々の食べ物が、お金を出せば、24時間お手軽に食べられる世の中になった。
きっと都会に住む年若き人々は、「コンビニやマクドナルドの存在しない社会」というものを、想像できないだろう。かつてそんな社会は存在していたし、そういう場所で子供に食事をさせる親は「失格だ」と言われていた。
「それらの食事」には、それなりの満足感はある。
しかし、その満足感は一過性のものだ。食べた後の記憶が残りにくい(ような気がする)。年をとってみると、その傾向が顕著になってくる。だから、「美味しい」とそれほど思えない食事をとる行為は、「エサを食べている」という感覚に近いように感じる。「食い物を胃袋に詰め込んでいる」という、義務的な感じがするのだ。
手作りの食事を食べる「美味しさ」と、チェーン店やコンビニの物を食べる「美味しさ」は、少し違う。そしてその「違い」が意識できない人が多くなってきているように感じる。
脳細胞には、記憶をつかさどる「海馬」という器官がある。
この海馬は、感情をともなうことで、整理され、より鮮明に記憶されるという性質をもっている。感情は「記憶の質」に影響すると、言われている。
「美味しい」
「嬉しい」
そう思いながら食事をすることで、人間は脳に記憶を刻む。
「本当に美味しいもの」を食べると、瞬間的に脳が活動し始める――気がする。喜び、驚愕、感激しながら食べる食事は、脳みそが喜んでいるというのか、驚いているというか、快感物質が分泌しているというか。
大げさに言えば、「美味しいなあ」「生きてて良かったなあ」と、実感することができたりする。でも日常、そう思えない食事の方が、ほとんどではないだろうか。
昨日の夕食を忘れたのは、飲みすぎていたのか、単なる脳の老化なのか。その食事は、美味しかったのか、楽しかったのか。
子供の頃から、味の濃い外食や、コンビニの弁当やパンや、マクドナルドのハンバーガーなんかを、「好き」だからといって食べさせ続けるということは、長い目で見てその子にとって、幸せなのだろうか。そんなことを、ふと考える。
別段、ファストフードに批判的なわけじゃない。食事を取る環境だって、記憶には大事だ。誰か好きな人たちと大勢で食べる食事だって、例えば塾帰りにみんなで食べる肉まんやアイスは、僕にだって美味しかったし記憶に残っている。
だから余計に、一人コンビニの前に座り込んで、ランドセルを背負いながらオニギリを食べている子供を見ると泣けてくるのだ。
悪いのは親だけじゃなくて、そんな社会システムを提供し甘んじている、僕ら自身なんだと思うと、やるせなくなる。たとえその子が、そういう食事を美味しいと思い、全然平気だったとしても。
冷凍のご飯と、炊き立てのご飯の美味しさは、断然違う。機械で作ったあつあつのオニギリより、お母さんが握ったけど、冷たくなったオニギリの方が美味しい世の中であって欲しい。
* * *
「あそこのカツ丼、結構すごかったんだよ」
「はあ。何がすごかったんですか?」
「大盛りでも普通でも同じ値段だ。まあ、従業員は無愛想なんやけどね」
「ほう。んじゃ、暇なときに行ってみます」
僕は何故か、聞かれもしないのに、自主的に自分が「美味しい」と思ったものを紹介する傾向がある。
自作した料理が「美味しい」とか「うまく出来た」と思ったら、誰彼構わず、作って無理やり食べさせようとする。
でもそれはきっと、彼ら彼女らにも、できれば「美味しい」と思い、共感し、心を動かして欲しいからなのだろう。どうでも良いお節介に過ぎないし、不毛な試みだとは思うのだ。
「どうやった?」
「とりたてて驚くほどのものでもなかったですが、それなりに美味かったですね」
「・・・ま、まあそれはそれでも良いのだ。食っていくうちに激烈に美味いと思う日がくるかもしれんしな」
「なんですかそりゃ」
* * *
大げさな話だということは、重々承知なのだが。
「美味いなあ」
「幸せだなあ」
という記憶の蓄積こそが、「生きていこう」と思えるための糧なのだと、僕は思いたい。
「美味しいねえ」
「幸せだねえ」
という記憶の共感こそが、「生きていこう」と思えるための糧なのだと、僕は思いたい。
「自分は、明日死んでも構わない」
そうつぶやく人を、本当に引き止められる言葉を僕は一つも知らないけれど。
「我が人生において、めちゃくちゃ美味いカツ丼を食わせる店を見つけたんだ。だから今度一緒に行こうぜ」
せめてそうやって、肩をぽんぽん叩こうと思う。
――いじきたないかもしれないけど。そういうもんの積み重ねが、「生きたい」って思うための根本なんだよ。きっと。
「美味しい」って思うことは、「嬉しい」って思うことは。
つまりは、そういうことなんだろう。
言葉では説明できないし、ウソ臭いから。美味しいもんでも食べて、美味しい酒でも飲んで。ただひたすらに肩を、ぽんぽん叩こう。
美味しかったらついでに、手も叩いとこう。
みんなで叩けば、幸せになれるらしいから。