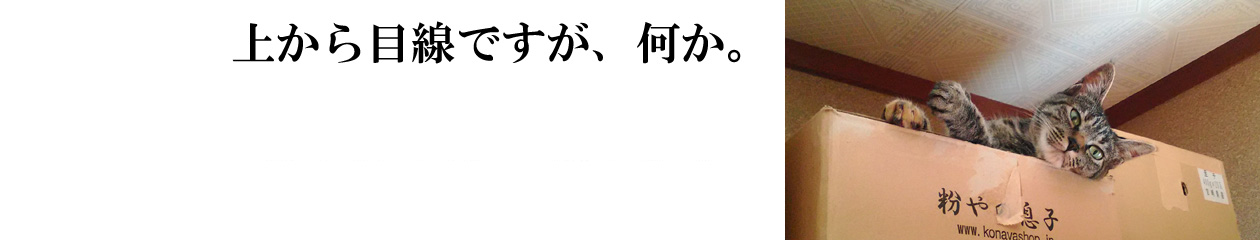船に乗り、瀬戸内海に浮かんでいた。
誰もいない深夜のフェリーのデッキで、夏の生暖かい潮風に吹かれながら、これを書いている。
土曜日だから乗客が多いことは予想していたけど、夏休み開けの九月だし、まさかそこまで多くもなかろうと思って乗り込んだら、そこまで多かった。
「個室は数が多く、予約しなくても大丈夫」
誰かのブログに書いてあったのでその通りにしたら、受付の人に「予約でいっぱいです」と言われて、あえなく撃沈。
船出早々縁起が悪い。いやそれでも予約すれば良かったのだから、「一から十まで」「おはようからおやすみまで」自分の責任なのだけれど。
「人だらけ」といっても、二等客室で窮屈に足を屈めて横になることくらいはできる。
さっきまでそうやって横になっていたが、自分は体が窮屈だと眠ることができない。
暗くて、静かで、体の上に程良い重量の何かがかかっていないと眠れない。車でも電車でも眠ることができない。無駄にデリケートだ。隣の人のように鼾をかくこともできない。
なので、ウロチョロしながらデッキまでのぼってきた。
一人で見る、夜の闇が大好きだ。
静かで、暗くて、誰にも邪魔されない。
フェリーのデッキから眺める闇夜の遠望は、水平線に沿って街の明かりしか見えない。夜の船は暗闇を割き、海面を見下ろせば、立つ白波に吸い込まれそうになる。
船に乗ってデッキから下を見るたび、「ここから落ちて海に吸い込まれたら、自分はどうなるだろう」と想像する。
想像しては、もし海に落ちたらどうしよう、あそこにある救命ボートへ走ろう。満員で乗れなかったらどうしよう。何か浮かびそうな積荷はあるだろうか・・・。
小学生の頃から、変わらず同じだ。
* * *
小学生の頃、夏休みなると隔年で、母方の田舎に帰省していた。
帰省は新幹線ではなく、船を使っていた。経済的な理由ではなく、僕の乗り物酔いがひどかったからだ。
最初に母が僕を連れて新幹線で熊本まで帰省した時、小さな僕は真っ青な顔で福岡まで泣き続けたらしい。それ以来、我が家では帰省といえば大阪から大分までの船旅になった。
小さい頃から、フェリーだろうが小型船だろうが釣り舟だろうが、いくら揺れようが、船にだけは酔わなかった。
一般的には揺れが強い乗り物の方が酔いやすいので、母は僕の事を「変な子供だ」と言っていた。
ただ帰る度に釣り舟を出してくれた田舎の叔父は、「この子には天草の船乗りの血が流れてるから、船に強いんだ」と、夜の宴の最中、赤ら顔で笑って言ってくれた。「そうやねえ」と母も同意し、一緒に帰省していた大阪の叔母も「きっとそうやわ。大人になったら、船運転したらええねん」と、頭を撫でてくれた。
大切に見守られていたなと、今更ながらに思う。
大人になった僕は、それほどまでに守るべき人々を、大切に見守れているだろうか。
小さい頃から、遠足だ社会見学だとバスに乗っては、酔ってフラフラになる自分が情けなかった。遠足が嫌いで、酔い止め薬が効いたという記憶はない。
いつも気分が悪くて泣いていたが、半分は情けなくて泣いていた。
バスの席決めは、いつも自然と前の席に決められた。そのことで虐められたことはなかったが、クラスの子に「大丈夫?」と心配される自分が情けなかった。
だから、田舎の叔父が言ってくれた何気ない一言が、小さな僕には誇らしく思えた。何も胸が張れなかった小さな僕に、与えられた数少ない栄光だったのだ。
大人の何気ない一言は、子供にとって、時に傷となり、時に勲章になる。
昨日会った甥っ子が、夕食前に買ってきたパンを四つ食べてしまったから「そんなに食べたら、また夕飯食べれないぞ!」と怒ったけど、「四つも食べれるなんて凄いな!」と誉めてあげたら良かった。
姪っ子が「外食したい。うどん食べたい」と駄々をこねてたけど、「うどん好きなんやな」と、頭を撫でてあげたら良かった。
駄目だ駄目だと言うよりは、良いことを見つけてあげて「良い」と言ってあげた方がいい。
それを取捨選択して、自分の中に取り込むかどうかは、その子が決めればいいことだ。
そうして人から人に、良いことを誉めて伝播していけば愛が溢れた世の中に…本気でそう思えるほどお気楽じゃないけれど、少なくとも世の中はその方が住みやすかろう。
自分の事で精一杯で、忙しく流れて焦って言い訳するより、よっぽどいい世の中だ。
香川に渡る船で、そんなことを考えた。
手始めに、姪っ子の食べたがっていたうどんを、お土産に買って帰ろうと思う。