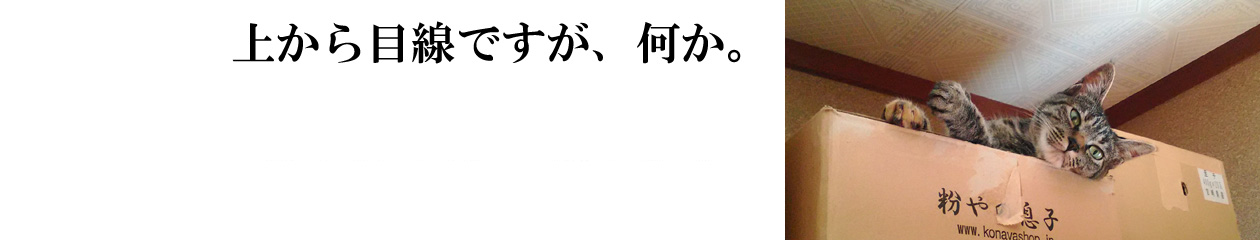読者の方から、「重松清の『きよしこ』という小説を、読んでみて下さい」というメールをいただいたことがある。
その小説を本屋で探し、少し立ち読みをし、文庫本を買って読んだ。
何故、僕が読んでみようと思ったのかといえば――その人が「本が好きです」と過去、熱い想いを綴ってくれたことがあったからだ。僕が本について書いた話に、同意してくれたからだ。
その言葉を信じ、「読んでみよう」と思った。
メールは「言葉」だけの世界でだから、伝わることもあり伝わらないこともあり、誤解したり誤解されたりする。
でも、「言葉」をやりとりした時間が、その人との間に、形にならない「何か」を作るときもあるのだ。
* * *
『きよしこ』という小説は、父親の仕事の都合で、小学校を転校ばかりしている少年「きよし」が主人公だ。
きよしは、自分の想いを言葉にしようとしても、ある特定の単語が出ない吃音の少年だ。「どもる」ことでクラスのみんなに笑われてしまい、無口になり、自分の気持ちを押し殺して生きている。満足に「自分の想いを言葉にすること」ができず、同情されるのを嫌い、それを隠すために人より多く悩み、傷つき、考えている。引っ越しが多くて、理解してもらえる友人関係をうまく築けない――そんな「きよし」少年の心の成長を描いた、優しい物語だった。
作者である重松清に、ある読者から手紙が来る冒頭部分のくだりがある。
読者はある少年のお母さんで、自分の小学校一年生になる息子が、重松清と同じ言葉をうまく話せない「吃音」で、クラスメイトからいつもからかわれているという。お母さんは、重松清にこうお願いする。うまくしゃべれないせいで引っ込み思案の息子に、どうか手紙を書いてはもらえないか――。
重松清は数日迷いながら、結局その少年に手紙を送らなかった。そのかわりにこの小説を書いた、とある。
「参考になる話はそれなりにできるかもしれない。教訓めいた話だって、一つや二つはあるだろう。でも、ぼくはぼくで、君は君だ。君を励ましたり支えたりするものは、君自身の中にしかない」
* * *
岩波新書に『ことばと文化』という本がある。
鈴木孝夫という人が書いた本で、若干堅苦しい内容だけど、僕にとってはかけがえのない大切な一冊だ。何年も前に読んだ本で、今でも手元に置いてある。
なぜこの本を、その昔の僕が手に取ったのか、よく覚えていない。
きっとその頃、僕は言葉に相当こだわっていたのだろう。もしかしたら親しい人と、やりたくもない口喧嘩を繰り返し、「どうやったら自分の想いを相手に伝えることができるのだろう」と、悩んでいたのかもしれない。
実際、そうなのだけれど。
その本に、次のようなくだりがある。
「――『犬』を例にとって考えてみよう。以前に犬に咬まれたことがある人と、そうでない人では、『犬』ということばに対する気持ちがちがうだろうし、犬が好きな人は、いろいろな種類の犬を見分けることも、性質のちがいを指摘することもできるが、犬に無関心な人にはこれができない。しかしどちらの人も『犬』ということばを理解し、使うことができるという点では同じである」
そして最後にこう結ぶのである。
ことばの『意味』は、個人個人によって、非常に違っている。
ことばの『意味』は、ことばによって伝達することはできない。
自分が普段何気なく使っている「言葉」の意味が、すぐ隣にいる人と少し違っている――それは、当時の僕には大きな自己崩壊だった。
僕らは普段使っている言葉を、小さい頃、無意識のうちに覚えた。
お父さんと話し、お母さんと話し、マネをしながら少しずつ少しずつ、覚えたはずだ。お父さんが好きだった子供は「お父さん」という言葉も好きなはずだけれど、お父さんが嫌いだった子は、「お父さん」という言葉も嫌いになってしまったのかもしれない。
同じ日本語を話していても、人によって記憶した言葉の歴史が違う。お父さんとお母さんが、それぞれの人で性格が違うように。友達や恋人が違うように。それぞれの人間は、それぞれの想いを胸に、言葉を紡ぎ生きてきたのだ。
でもなかなか、人は相手の気持ちになって、相手の立場になって、言葉を受け止めることはできない。自分勝手に言葉を解釈し、怒り、相手の想いを踏みにじり、そして時には相手との関係を絶ったりする。
「自分の言った『言葉』が、相手によって違って解釈されるとすれば・・・それはいさかいも起こるし、分かり合えることもできない。何より、自分の想いを相手に伝えることも、できないじゃないか」
この本は、僕に「言葉」を使う怖さや大切さを、教えてくれた。
自分が語る「言葉」が、相手にどう伝わったか、考えてみたことはあるか?
相手がどう受け止めるのか、相手がどういう人なのか、考えてみたことはあるか?
もし相手が自分の言葉を誤解して受け止めたとして、それは誤解した相手が悪いのか?
本が、そう問いかけてくる。
そうして、言葉は「話す」よりも、「聴く」方が数十倍も難しくて、大切なんだと知った。
えてしてそういう時は、大切だった人と別れた後だったりするのだけれど。
* * *
「強い物語があって初めて人に伝わるし、感情に訴えないとメッセージは咀嚼されない」
(アリス・ウォーカー 日経新聞インタビュー)
* * *
小説や物語は、なぜこの世にあるのだろうか。
言いたいことや、伝えたいこと。直接ハッキリ言えば良い。
「人に優しく」だとか。
「元気を出して」だとか。
「勇気を持って」だとか。
何百頁もかけて、結局言いたいことをハッキリ言わない。最短距離で、伝えれば良い。
でも僕ら人間は、呆れるほどに「分からず屋」で。
他人のことに無関心で。例えありがたい助言をもらったところで、頭で理解はしていても、心にまでは響かない。
「とおまわり」しなければ、「分からず屋」の僕たちの心まで、届かないものがある。
小説は、言葉にすれば伝わらない「何か」を、言葉を沢山使って登場人物を沢山出して、情景描写を綺麗に書いて、「とおまわり」しながら、読む人の心に伝える。
重松清は作家だから、「言葉」で自分の想いを相手に伝えるには、「とおまわり」するしかないと知っている。
だから、『きよしこ』という小説を書いた。自分と同じ吃音で苦しんでいる少年に、願いを込め、小説一冊分の「とおまわり」をして伝えようとした。
「自分は孤独なんだ」と思い込んでいる世の中の「分からず屋」に、「独りぼっちの人間なんて、本当はいないんだ」という真実を、力一杯、物語を通して叫ぶ。
想いが、伝わらなくても。いつか相手の中の「分からず屋」も、理解するときが来るだろう。自分の中の「分からず屋」も、いいかげん思い知るときが来るだろう。
仮に言葉が相手に届かなくても。
許せる自分になれるのだろう。優しい自分になれるのだろう。
自分の足で「とおまわり」しなければ、見つけられない景色もあるのだろう。
「とおまわり」した分だけ、人は優しくなれる。
そう僕は、信じている。