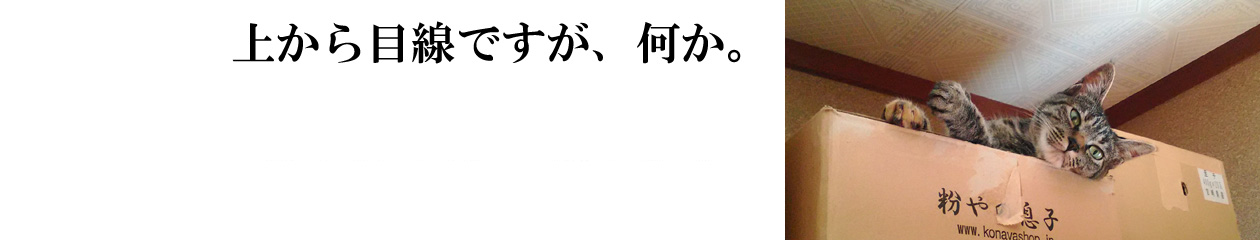夕暮れ時。ガスタンクを見ていた。
川沿い、夕暮れ、町外れ。近くでは大規模な公共事業。
人通りの少なくなった、薄暗い時刻にたたずむ、いい年した男が一人。
買い物帰りの主婦と、その手を引かれた子供がこちらを見て、あきらかに警戒している。目にぬくもりがない。いいぞ。正しい判断だ。どこからどう見ても怪しい人にしか見えないだろう。
足早に横を過ぎていくお母さんの警戒心が、少し切ない。振り返り振り返りこちらを見る子供の好奇心は、少し微笑ましい。
夕暮れ時。ガスタンクを見ていた。
* * *
町はずれにあるガスタンクが、転がってしまうんじゃないかと考えていたことがあった。
あんなにも巨大でまぁるいものが、制止していることが不思議だった。小学生低学年ながらに、球体は不安定で、基本的に転がるものだと理解していたから、やがてあのガスタンクは、一つ地震でも起きようものなら、転がって転がって転がって僕たちに襲いかかり、スルメのようにペチャンコに押しつぶしてしまう――そう考えていた小さい頃の僕は、ガスタンクの側を通るのが怖かった。
妄想がちな小学生だった。
だから、ガスタンクのそばを通るときは、母親の手を泣きながら引っ張っていた。
「あんた、何泣いてんの!」
「だって、転がって二人ともひかれるやんか!」
母親は、笑いながら僕に手をひっぱられつつ、その様子が面白かったので意地悪に立ち止まって、僕をさらに泣かせていた。僕のSの血は多分母譲りなのであろう。
同じように、電車の踏切も怖くて、これはよく覚えていて、小学生の僕は、泣きながら母の手を引いてグイグイ渡ろうとしていた。
「カンカンカン・・・」
あの警告音が鳴り出すと、泣き出していた。
泣きながら母親の手を引っ張る。ここでも彼女は「大丈夫やて」と笑いながら立ち往生していた。僕の中のSの血はきっと母譲りなのであろう。
ガスタンクに押しつぶされるのが怖かった。
電車に轢かれるのが怖かった。
振り返ると変なガキだったなと思える。自分一人で、逃げようとしないガキだったんだと思うと、少し安心する。自分が死ぬのも嫌だけど、母親が死んでしまうのを見るのも、嫌だったのだろう。
まあ、あくまで妄想の中での話ではあるのだが。
* * *
大人になってガスタンクを見てみると。不思議な建造物だと思ってしまう。
何であんな球体をしている必要があるのか。
きっと、すべての壁に均一に圧力をかける必要があるんじゃないかなとか、強度の問題かなあとか、大人なりの憶測をすることはできるのだが、それにしても人間はよくあんなものを造り出せるもんだと感心してしまう。
高速道路にしても、海にかかる橋にしても、山深くにあるダムにしても、山の斜面にそびえる送電塔にしても。造る労力や期間を想像して、途方に暮れてしまうときがある。
ガスタンクなんて、丸くて巨大なのだ。よくあんなものを造ろうと考えたものだ。初めに「ガスを貯める」ありき、なのだから。
作家坂口安吾が『日本文化私観』というエッセイの中で、「美」に対する考察をするところがある。
安吾はその中で、旅先で見た、刑務所とドライアイス工場と軍艦を見て「美」を意識する。
「この三つのものが、なぜ、かくも美しいか。ここには、美しくするために加工した美しさが、一切ない。美というものの立場から附加えた一本の柱も鋼鉄もなく、美しくないという理由によって取去った一本の柱も鋼鉄もない。ただ必要なもののみが、必要な場所に置かれた。そうして、不要なる物はすべて除かれ、必要のみが要求する独自の形が出来上っているのである(中略)
すべては、ただ、必要ということだ。そのほかのどのような旧来の観念も、この必要のやむべからざる生成をはばむ力とは成り得なかった。そうして、ここに、何物にも似ない三つのものが出来上ったのである」
(坂口安吾『日本文化史観』引用)
安吾は、芸術とはそういうものでなくてはならない、と説く。
「美しく作ろう」と意識した時点で、それはもう美しくない、と言っている。
ガスタンクを見ながら、そんな一文を思い出していた。
夕暮れに映えるガスタンクを、美しいと思った。
夕暮れが美しいのだろうけれど、奇妙な形のガスタンクがそこにあるという絵は、自然と人間が偶然作り出したもので、意図されてできたものではないのだ。
人間はきっと、目で見えるものだけで「美しい」とは感じないのだろう。でもなんだか今の世の中は、少し目で見えるものばかりに、振り回されすぎているんじゃないかと思える。
安吾が生きていたら、今の世の中を見てどう思うんだろう。少し知りたいと思った。恐山に行って、イタコに聞いてもらおうか。
* * *
夕暮れ時。ガスタンクを見ていた。
大人になった僕は、これが転がるわけないと知っている。だから怖くはないし、泣きわめくこともない。誰かの手を引っ張って、その場を去ろうとすることもない。踏切が鳴り出しても、歩いている始末。
大人になっちまいましたなと、少し切ない思いが胸をよぎる。
振り返って、そんな小さい頃の自分の行動が、ピュアだったなと思うことができる。母親の気を引こうとか、よい子に見せようとか、そういう気持ちが裏にあったわけではないからだ。
怖かった。死にたくなかった。死んで欲しくなかった。だから幼い僕は、泣きながら手を引いた。
母は、きっと嬉しかったに違いない。照れ隠しに、僕に意地悪してたんじゃないか。
大人になって、少しそんなことを考える。
さっきの子供が、遠くでまだ僕を振り返って見ていた。
今はお母さんに手を引っ張られててもいいけど。
いつかは、自分で手を引っ張らなきゃいけないよ。
そんな上から目線の妄想を抱きつつ、本当に変質者に間違われても困るし、夕日が背中を押してくるので、とっとと家に帰ることにした。