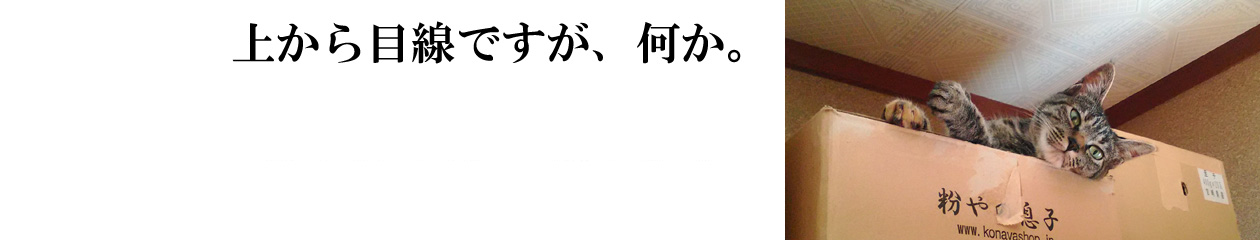小学生の頃、ずっとタマネギをスライスしていた。
二つに割って量端を切り取り、外皮をはいで水洗いした後、包丁で薄くスライスしていく――。
それが母から最初に教わった、野菜の切り方だった。タマネギを薄く切ることだけが、当時の僕の料理のすべてだった。
大した理由ではない。当時、インスタントラーメンに入れる具が、ほぼタマネギのスライスだったのだ。
毎月、淡路島の農家が軽トラックで野菜を売りに来ていたため、タマネギだけは大量に家にあった。
「インスタントは栄養が偏るから、食べるならなるべく具を入れろ」と母から忠告を受けたからでもある。薄く切るのは早く煮えるためだとか。
「インスタントなんやから、時間かかったら面倒やろ?」と母は言っていた。なるほど、と僕は思った。
* * *
幼稚園のころ、初めて自分で袋のインスタントラーメンを作った。
近所にいた一つ上のお兄ちゃんにインスタントラーメンをご馳走になり、自分でも作りたいと母に直訴した。そのお兄ちゃんの作った袋のラーメンは、麺が非常に固かった。それでも自分で作れるなんてすごいなあ、と幼稚園児ながらに感心していた。
「麺を長く茹でればいいんだ」と思った。
母にラーメンを作らせてくれと頼むと、「とりあえず見ててやるから作ってみろ」と言って、じっと戦況を見守っていた。
そうはいっても幼稚園児。鍋に水を入れるところからして、どれだけ入れたらいいのか分からない。母に聞くと「適当でいい」と分量もはからず、蛇口からそのまま鍋に水を入れ、コンロにくべた。
どうにかこうにか作ったラーメンを、鍋からドンブリに移して食べると、それは今まで母が作ってくれていたラーメンの味と、ほぼ遜色なかった。
母は横から一口食べ、「上出来や」と笑った。
初めてタマネギをスライスしたとき、包丁が怖くてうまく切れなかった。
不器用に切った僕のタマネギを見て、母は言った。
「厚く切ってもうたら長く煮ればええ。あんたは男なんやから、食べれたらそれでええねん。結婚してときどきでも自分で料理して食べてくれたら、それだけで嫁さんはありがたいんやで」
料理がうまくなりたいと思ったことはなかった。だが延々とタマネギをスライスしていくうち、「包丁はこうやれば切れやすいんだな」などと分かるようになった。
少し自信を持つと、他の野菜も切ってみたくなった。
インスタントラーメンの具になりそうな野菜から、扱い方や切り方を伝授された。キャベツの芯を棄てるのはもったいないと僕が言うと、
「ほな炒めてラーメンの上にのせるか。その方が美味しなるわ」とフライパンの使い方を仕込まれた。
そのうち肉の扱いも仕込まれ、野菜炒めができるようになり、焼きそばの作り方に発展した。麺の煮込み方の応用から、タマネギの具で味噌汁の作り方を教わり、次いでカレーを作れるようになった。インスタントラーメンを足がかりに、僕は料理のレパートリーを少しずつ広げていった。
共働きで鍵っ子だった僕は、ときどき勝手にカレーを作った。仕事から帰った母に「助かるわ」と誉められたりした。小遣い目的の行動ではあったのだが、褒められると単純に嬉しかった。
* * *
母の通夜の席で、親戚のおばさんから「お母さん料理上手やったから。もうあの味、食べられへんね。寂しいやろ」と、よく慰められた。
その度に「僕は小さい頃からずっと料理仕込まれてたから。母親の味は再現できるよ」と答えていた。そう言うと、おばさんたちが安心した顔をしたからだ。
本当は、再現できるのは良くて10品程度だった。「男の料理は適当でええ」というスタンスで僕に料理を仕込んだのが、アダになった形だ。
死ぬ何年も前から、母親は手が動かなくなっていた。好きな料理ができなくなった母親に僕は、
「教わってない料理は、俺ができる限り覚えたる。もう料理できへんこと、グジグジ言いな」と言った。
「それやったら、もういつ死んでもええわなあ」
「そんなつまらん事口走るなら、もう覚えたれへんわ。勝手に死んどけ」
どちらも最後まで素直じゃなかったので、結局僕は母の料理を全部教わることはできなかった。筑前煮やちらし寿司の味は覚えているが、もう再現させることはできない。
* * *
料理好きの母は、兄が生まれた次は女の子が欲しかったらしい。
そして自分の料理を教えることを楽しみにしていた。しかし生まれた僕は男で口が悪く、天の邪鬼で言うことを聞かない、クソガキだった。
何かにつけて僕に小言を繰り返していた母だったが、こと料理に関しては「ダメだ」とか「下手だ」とか、一切言わなかった。ああしろこうしろと指図することもなかった。料理法を押しつけることもなかった。
自分で作ったものの、マズくて食えなかった料理を棄てようとしたら、「棄てるな、私が食べる」といって母は食べた。
「味付け間違えたかな。でも十分食べれる」
そう言って、パクパク食べた。そして、なぜ美味しく作れなかったのかを僕に教えた。
「男子厨房に入るべからず」の時代に育った母ではあったが、僕に料理を教えることは嬉しかったらしい。
だから、僕の料理の基本は、インスタントラーメンを食べるために延々と切り続けた、タマネギスライスにある。
「上手にできなくていいから、とりあえず作ってみなさい」
押しつけず、良いところだけを誉めた母に、僕は料理を仕込まれた。家庭の料理が一番美味しい理由と一緒に。
毎日の食事は、黙って勝手に出てくるものではないということを。
作ってもらった料理は、それだけで十分嬉しく、ありがたいものなのだということを。
作ることと食べることは、みんなの「共同作業」なのだということを。
料理を通して教えてくれていたのだろうと、遅まきながらにそう思う。