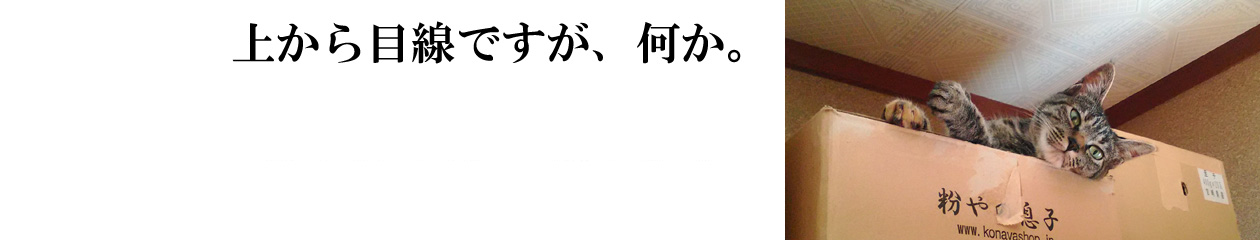「自分にできることは、何だろう」
高校生の頃、よく自問自答していた。そんなに勉強ができる訳でもなく、運動ができる訳でもない。背が高い訳でもなく、顔がいい訳でもなく、社交的な性格でもない。
中途半端な人間で、自分のそんな「中途半端さ」が、いつも不満だった。
高校時代は演劇部に所属していたが、演技がしたくて入部した訳ではなく、廃部を免れるために先輩に強引に押し込まれ、そのまま居着いただけだった。三年間の発声練習のおかげで通る声を出すことができ、大舞台に立たされても緊張はするもののアドリブをきかせるだけの度胸も持てた。でも、「演技の道を極めたい」と思ったことは一度もなかった。
卒業して残った僕の「武器」は、せいぜいソラで「外郎売り」や「アメンボ赤いなあいうえお」をやれることくらいだ。昔、忘年会の隠し芸でやらされ、少しだけウケた程度だ。
「武器が欲しい」と思っていた。
他人に誇れて、自分も納得できるだけの「武器」が欲しかった。今思うとそれは、単に認められたかったのだろう。「すごいすごい」と言われたかったのだろう。
世間に。親に。兄弟に。友達に。別れた恋人に。
そして誰より、大嫌いだった、自分自身に。
「文学部に入れば、文章力を身につけることができるはずだ」
そう思い、大学生になり文学部に滑り込んだら、文学部が「文章力」を身につける場所ではなく、「文学を研究する場所だ」と知った。知った時は既に遅かった。
それでも何かと教授方に目をかけていただき、全学年の担当教授に「大学院に進め」と声をかけていただいた。なのに、世間知らずで他人にかかわることもかかわられることも嫌いだった当時の生意気な僕は、曖昧な返事をして聞き流した。「文学」という武器は、特に欲しいと思っていなかったのだ。
コンピュータの仕事をしてた時も、自分の思うような仕事をさせてもらえず、「コンピュータの専門家になりたい」と思っていた自分の意に反していた。だから辞めた。
僕の人生は、「自分の武器を見つけるための旅」だった。しかしすべては、中途半端に終わった。
文章力が欲しいと望んだが、上の才能には追い付けないと自分勝手に諦めた。コンピュータも人並みレベルの知識と才能だ。料理の腕も素人で自己満足の世界だし、文学を語れるほどに本を読んでない。
何から何まで。一から十まで。
「中途半端」な人間だった。
* * *
ロールプレイングゲームの武器では、「エクスカリバー」が好きだった。
岩に突き刺さる伝説の聖剣。剣に選ばれた勇者だけが、その剣を抜くことができる。誰もが欲しがり、誰もが求め、手にしたものは誰からも賞賛を浴びる。
でも僕が現実に手にした剣は、せいぜい「どうのつるぎ」だ。
こん棒でスライムをひたすら叩き、ある程度お金をためたら買える一番安い剣。「てつのつるぎ」までの繋ぎ程度で、人によればこん棒で我慢してお金をため、一つ飛ばして「てつのつるぎ」を買われてしまうため、使わないで終わる人もいる。誰でも持てる普通の剣。せいぜい、最初の街から次の街まで移動する程度にしか活躍しない武器屋の定番商品。終盤の宝箱で出ると、「ドラゴンキラーじゃねえのかよ!」と捨てられる、「やくそう」より価値の低い剣。
エクスカリバーを求めて中途半端ながら旅を重ね、敵と戦い、敵から逃げ、人を助け、裏切られ、嘘をつき、お金をかせぎ、お金を浪費し。
その結果、僕の右手に垂れ下がった、普通の「どうのつるぎ」。
しかし、その剣が。他の人と同じではない。この部分がサビている。こうやって使うといい感じに振れる。好きだと言ってくれる人もいる。そんな風に、この世に一本の自分の「つるぎ」なのだと気づけたこと。
その「目」と「心」こそが、僕の「武器」になっていた。
人から「ただのどうのつるぎじゃないか」と言われても、決して卑屈にならずに前を向ける。「ただのどうのつるぎでしかない」と落ち込んでいる人に、その良さを教えてあげることができる。
それこそが僕の「武器」だと、知ることができた。
* * *
就職で、悩んでいる人がいる。
久しぶりに出したメールで、そんな話を聞いた。
公務員の試験を受けるその人は、一生懸命に勉強していると思う。謙虚な性格だから「全然できていない」「さぼっている」と言うかもしれない。でも少なくとも、一生懸命やらず、現実から逃げている人よりは、努力しているはずだ。会わなくても、そう確信することができる。そういう人だったからだ。
落ちると怖いだろう。周囲の友人と違うことをしている自分に、焦っているかもしれない。だから僕には、「大丈夫」とか「絶対受かる」とか、無責任なことは言えない。現実は厳しい。落ちるかもしれない。人生どうなるかなんて、誰にも予想できるものではない。
こういうとき僕は、その人の気持ちをせめて一ミリグラムでも軽くしてあげられないか、と思う。
だから、今回の話を書いてみた。
その人の重圧が、軽くなるかは分からない。ただ、「軽くなって欲しい」と思いながら書いた。
「聖剣を探す旅に出て、旅路を悩んでいる。それだけで君は、ものすごく正しい道を選び、歩いているのだよ」
僕はその人が、正しい目と心を持っているということを、よく知っている。
きっとその人は、聖剣エクスカリバーを探す旅路の果てに、自分の持つ「武器」を正しく認めることができるはずだ。
僕の中には、「年寄りのやるべき仕事」の定義がある。
「俺は、エクスカリバーを探しに行くんだ」とか、「ドラゴンキラーを手にしてドラゴンを倒しに行く」とか、大言壮語している若者に、「どうのつるぎ」の良さを話し聞かせ、旅に出ることを諦めさせること…。
では、決してない。
その旅が、どんなに素晴らしいものであるかを、言って聞かせることだ。「君の旅は、正しいのだ」と、認めてあげることだ。
旅人の仕事は、ドアを開けた時点でほとんど終わっている。
それだけで、その人は胸を張っていいのだ。