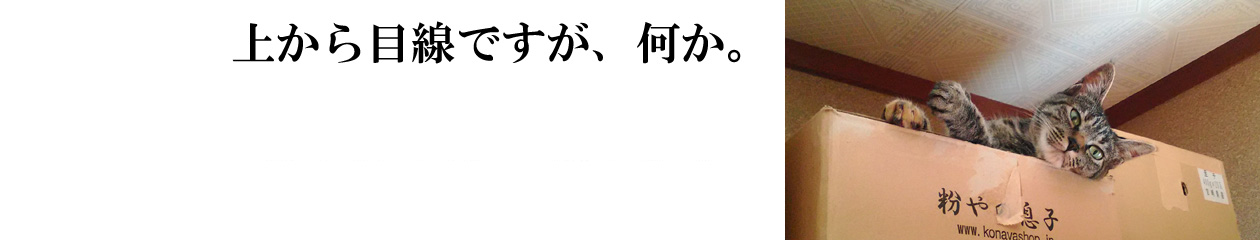「あのコのこと、大嫌いです」
おでこにシワを寄せながら、彼女は僕にそう言った。
「私、あのコとあわへんのやわ。もう顔見るのも嫌。一緒に仕事すんの、もぉー嫌っ」
彼女は、いかに自分が相手を嫌っているかを、一生懸命僕に伝えようとしている。
その一生懸命なエネルギーをどうして他に使わないの? というような疑問は、おくびにも女子の前に出してはならない。
「まあまあ。そう安易に人を嫌うもんじゃないよ。来年には学校卒業して社会人になるんだろ」
とりあえず、一息入れてみる。
「何でですか?」
「だって、ほらさぁ。仕事なんやから、嫌いってだけで、一緒に働かん訳にもいかんやんか」
「でもあのコ、私がちょっと注意しただけでムクれるんですよ! 優しく言ったら何もしないし。ホンマ、使えへんわー」
「あのコかて、この仕事しだして間ぁないしさ。緊張してるだけやって。緊張してる顔が、怒ってるように見える人って、おるやんか。俺も、結構そうやし。君に怒られて固まって、その顔がムクれてるように見えるだけやと思うよ」
「Tさん」
「何」
「何で、あのコの肩持つんですか?」
刃はいつしか、しかし確実に僕の方に向きはじめた。彼女の血塗られた刃は、獲物であればなんでもぶった切ることを少し忘れていた。
「・・・か。肩なんて持ってるつもりは、ないよ」
「いーや、持ってる。Tさんはアイツと働いたことないから、そんなオキラクなこと言えるんや!」
「持ってないってば。そんなん言うなら、俺は君のワガママ、どんだけ聞いてきたと思ってるんだ。俺はその新人のコのワガママを、長い付き合いの君ほど聞いてはいない! どっちか言うたら、肩持たれてるのは自分の方やろ!」
「何で、私がTさんに怒られなあかんの!」
「いっこも怒っとらんがな! これは怒ってるんやなくて、熱弁や!」
「もう!」
やり場のないエネルギーが、完全に僕へ向いた。
「あのコが怒ってるとか、なんで仕事ができへんのかとか、そんなんどうでもいいんです! 同意してくれたっていいじゃないですか! 一緒に悪口言うてくれたらそれで終わりやのに、何で私の味方になってくれへんのですか!」
怒りに満ちた目で、彼女は僕にそう詰め寄った。
相手が安心して僕にキレているのを見て――仲良くなるのも考えものだな、と脱力した。
* * *
ゲンジボタルという蛍がいる。
ヘイケボタルという蛍もいる。日本で生息している蛍は他にもいるが、主にこの二種類に分かれる。川で蛍を見たからといって、その蛍が日本全国で同じ種の蛍というわけではない。
ゲンジボタルはヘイケボタルよりも大きく、灯す光も強く美しい。そして、水がきれいな山間部の渓流などに生息する。一方のヘイケボタルは、流れのゆるやかな小川や、水田や湿地に生息している。条件さえあえば、それぞれが同じ場所に生息することもある。
ゲンジボタルは、水の綺麗な川でしか住めない。川が汚れると、絶滅の危機に瀕してしまう。その理由は、ゲンジボタルの幼虫の食べるエサにある。
ゲンジボタルの幼虫が食べるエサは、「カワニナ」と呼ばれる貝。それしか食べない。そのカワニナは、水の綺麗な川にしか生息できない。
一方、ヘイケボタルは、少々の環境変化にも耐えうる強靭さを持つ。それは、ある程度の生活環境の変化や条件等によって、自分たちの食性を変化させることができるからだといわれる。
ヘイケボタルは、カワニナ以外にも様々なエサを食べる。タニシやモノアラガイ、時と場合によってはプランクトンや死んだドジョウやヤゴなどを食べるケースもある。その「雑食性」ゆえに、生存能力はゲンジボタルよりも高いのだ。
ゲンジボタルは、ヘイケボタルにくらべて環境の変化に敏感で、弱い。手厚く保護してやらなければ、すぐに絶滅してしまう恐れがある。保護運動などで守られているのは、ほとんどがこのゲンジボタルだ。
「絶滅した蛍が、努力のかいもあって、私たちの地域に戻ってきました」
そんなニュースを見たからといって、戻ってきたのがゲンジボタルだとは、限らない。
* * *
「は? だから、何なんすか?」
あきれかえった目で、彼女は僕に言った。
「え?」
「だーかーらー。突然、蛍の話なんてし出して、何だってんですか!?」
「えーと知ってる? 蛍ってね、成虫になると、水しかなめないんだ。エサが必要なのは、幼虫の間だけなんだよ」
「そんなん聞いとらん!」
「いや、だからやね。つまり君も、ゲンジボタルではなくヘイケボタルになろうよ、と。そう言いたかったんだよ」
「は。何言ってるんですか?」
世界中のうんざりした人々の代表であるかのような、とてもあきれかえった目を再度向け、彼女は言った。
「一種類のエサしか食べられないゲンジボタルは、そのエサのカワニナがなけりゃ絶滅するんだ。生き延びるためには、ヘイケボタルみたいに、どんなエサでも好き嫌いせず、食べられるようにしないといけないんだ。それが生物の真理だ。『エサ』ってのはこの場合、人間関係だ。誰が嫌い、誰と一緒にいたくない、あれが嫌、これが嫌って好き嫌いしてたら、何もできない。必要以上に他人を嫌って、他人とぶつかったり避けたりばっかしてたら、生き辛いだけだ。相手の良い部分見つけて、誰とでもある程度仲良くやっていかなきゃ」
「超絶、無理やわー!」
僕の意見は、音速の勢いで全却下された。
「あわへん人と仲良くするなんてできへんもん! 時間の無駄やわ!」
手を横に勢いよくぶんぶん振りながら、彼女は断言した。
「だったら、自分が絶滅するか、相手を絶滅させるかしか、ないでしょうに」
「相手を絶滅させたる!」
「いやいや」
「あー。私も、絶滅せぇへんように、誰かに手厚く保護されたい」
「もう勝手にせい」
そうして話は、いつものように冗談が混じり。
やがて冗談だけになり。
本質は何も解決されないまま、底に沈む。
* * *
僕は彼女の、恋人でもなんでもない。
友達と言えるほど、心を開きあっているわけでもない。仕事場が同じで、楽しく会話できる仲だという間柄でしかない。
それ以上でもそれ以下でもないし、それ以上にもそれ以下にもなれない。
となりで、彼女の頭の中が嫌なことでいっぱいになって、気が狂いそうになっても。僕に出来ることなど、ほとんどない。
彼女を救うことができるのは肉親か恋人か親友だけで、それ以外の中途半端な関係では、中途半端な結果にしかならない。
中途半端な親切は、迷惑でしかない。
彼女のことを分かってあげることは、必ずしも「救い」ではない。
だから会話の最後は冗談だらけになり、いつものように適当な距離を保って終る。
僕は、彼女が良い子だということを知っている。
誰とでも仲良くなりたい、仲良く暮らしたいのだ、ということも知っている。
本当はこれっぽっちも、他人を嫌いたくなどないのだ、ということも知っている。
人間関係が少し不器用で、必要以上に他人の顔を見てしまう、ということも知っている。
怒りは、恐れの裏返しだということも、知っている。今までの人生で、色々な人を嫌い、反発しあい、避けて生きてきたということも、知っている。
キライダ。
キライダ。
ダイキライダ。
そんな人生は、とてもしんどい。
「キライダ」という彼女に、同意するのは簡単だけど。それでは彼女が、自分の意識に目を向けることができない。
無駄であっても、嫌われても、右から左に流されても。
「同意しないこと」が、他人である僕にできる、たった一つの選択肢だ。
無駄になること。嫌われること。右から左に流されること。
一歩間違えればセクハラでしかないかもしれないが、そこは誠実に培ってきた信頼感に頼る他はない。
肉親でも恋人でも友人でもない僕に出来るのは、嫌われることを覚悟で、気付いてもらおうとすることぐらいしかないのだ。
彼女には少しでも、生き易い社会を歩んで欲しいと思う。
「キライ」で溢れた社会じゃなく。
「スキ」で溢れた社会を、見ようとして欲しい。
「スキ」ではないにしても、せめて「キライではない」程度に、薄まるように。
食べて自分の栄養にして、この面倒くさい世の中を、生き抜いて欲しい。
夏の夜に光る蛍のように。
輝く笑顔で、社会に羽ばたいて欲しいなあと願う。