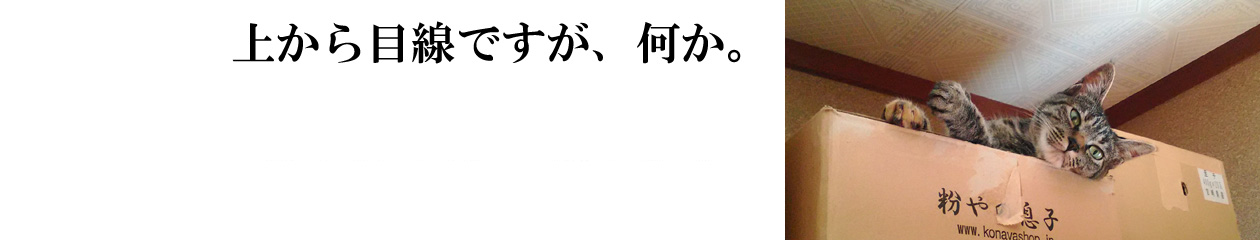ある女性が、僕に言った。
「つきあってる彼氏がいます。結婚も考えています。でも彼は『僕は君と結婚する資格がない』と言います。理由を聞くと『僕は色覚異常なんだ』って。私が『そんなの全然気にしない。大丈夫だから』って言っても、彼はずっと悩んでいます。彼がなぜそんなに苦しむのか、私には分からないのです」
* * *
僕は色覚異常、一昔前で言う、いわゆる『色盲』だ。
正確には「先天赤緑色覚異常」と分類され、赤や緑が混ざった色はほぼ分からない。程度が軽い人は「色弱」と呼ばれるが、僕は眼科医から「色弱と呼べるほど軽くない」と小さいころに宣言されている。
程度が軽い人は色覚異常と診断されないこともある。宣言される人は、幼少のころから自覚症状を持つほど重い人だ。症状は複雑であり、色覚異常者同士で同じ見え方はしないという。
ほぼ症状が出るのは男。そして色覚異常は遺伝する。
昔から就職差別や結婚差別、様々な偏見は後を絶たない。なくなってきているが、今でもちらほら見受けられる。
欧米では色覚異常は”異常”ではなく”普通”であり、差別や偏見を持っている国は日本だけだという。「だという」としか書けないのは、外国の本当の事情は分からないこと。そして僕自身このことに関して、差別や偏見や同情以外の接され方をしてこなかったので、分からないのだ。
色鉛筆は、軸に書いている色の名前で判断する。色の名前が書いていない色鉛筆は使わない。物を買うときも、相手に色で伝えない。間違うと知っているからだ。商品はいつも、指さすか自分で手に持って相手に渡す。
そんな僕のHPはほぼモノトーンだ。白と黒だけは、僕と正常者が同じように見えている、安心できる色だからだ。
そうやって生きていると、色を識別することに支障はあれど、日常生活にさしたる問題はない。事実、自分が色盲であることを、忘れてることの方が多い。
当然だ。他人と自分の見える世界を比較することなんてできないのだから。僕にとって、僕の見えている景色や世界のみが「真実」であり「現実」だ。
自分が忘れてしまう程度の障害のせいだろう。色覚異常は、正常者からほとんど理解されていない。
「自分は色覚異常だ」と宣言しても、相手の反応は「そうなの?」という程度の変化しかない。「自分の骨は折れている」と言えば反応は違うだろう。骨折の知識や現実は、普通の人ならイメージしやすい。
しかし、色覚異常はイメージしにくい。できなくて当たり前なのだ。だからこれは、「仕方がない」ことなのだ。
多くの色覚異常者は「分かってもらえないことは、仕方がないことだ」と思って生きてきている。偏見にせよ差別にせよ、相手は無意識だ。悪意がない。
でも色覚異常者は傷付いている。その傷を癒すためには「仕方がない」と思うしかない。そう思う以外に、心を落ち着かせる方法はないのだ。
大学時代、バスで一緒に帰る女の子がいた。その子は明るい子で、よくしゃべった。しゃべりすぎて時に口が滑ると、とても落ち込む子だった。
あるとき、バスの窓から当時世間を騒がせた宗教団体の店舗が見えた。僕が「あの黄色い屋根がそうかな?」というと、彼女は振り返って言った。
「黄色?嫌ね、あれは緑やないの。自分、色盲ちゃうの?」
満面の笑顔だった。彼女は冗談で言っている。
またかと僕は思う。ここで「そうだ僕は色盲だ」と言うのは簡単だ。でもそれを言えば、彼女は自分の軽口に傷つくだろう。彼女に悪意はない。
僕はひきつった顔で笑いながら、「ちょっと見にくかっただけや」とかわしながら、「仕方がない」と自分に言い聞かせた。
僕ら色覚異常者は、何気ない言葉が人を傷つけるということを、身をもって知っている。
「これは何色に見えますか?」
何気ないこの一言で色覚異常者は、時に体が震え、心拍数が増加し、心に傷を負う。それは、小さい頃の体験が影響しているかもしれない。
小学校にあがってすぐ、自分が色覚異常だと意識した。自分では分からない。自分が異常であることは、他人と比較して初めて意識できる。
小学校の美術の授業で、僕はクラスのみんなに「コイツ、変な色を塗っている。おかしい」と言われた。自分は見えている色を普通に絵の具で塗っただけだ。段々エスカレートするクラスのみんなに、先生が僕を呼び出し、クラス全員の前で言った。
「この子の目はみんなと色の見え方が違う。だから冷やかしてはいけません」
好奇心が旺盛な小学生は、休み時間に当然僕に聞いてくる。
「これ、何色に見える?」
答えられる訳がない。しかし、答えられないのは僕だけだ。答えられない自分は「異常だ」と思うのだ。
6才の子供がそう思い、助けてくれる人は誰もいない。僕の場合、母方の爺ちゃんが色盲だったため、親にも理解しては貰えなかった。
手がない人に「このリンゴを持って下さい」と言う人はいない。見れば分かるからだ。言う人がいれば、そこには悪意がある。
色覚異常は、相手に見えない。判別しようがない。相手に悪意はない。色覚異常者は傷つきながら、その刃を自分の内にしまい込む。
これは「仕方がない」ことなのだ。そう思いながら。
しかし自信は削られていく。色の質問をされると、自信のない自分が顔を出す。
「自分の今見えている世界は、偽物なのだ。みんなと自分は違うのだ」
その思いが、どんどん重ねられていく。その現実を、社会はどんどん押しつける。無関心と無理解が、自信を根こそぎ奪っていく。
そうして「自分は欠陥品なのだ」という劣等感が、自分の中にしっかりと根を下ろす。
幼少からそうやって生きてきた色覚異常者は、だから胸を張って「自分は普通です」と言うことができない。
「どれだけ頑張ってもできないことがある」ということを、小さい頃の現実と経験から身をもって知っている。
悪意がない言葉でも、人を傷つけることがある。
しかしそんなことをいちいち気にして、人は生きていけない。その人は悪くない。そして「仕方がない」と思う。頭では分かっているが心が拒絶する。
それを克服するには、人間を分かろうとするしかない。「仕方がない」ことが「当然のことだ」と思えるほど、強くなろうとするしかない。強がりではなく、ただ静かに、強くなろうとするしかない。
頭と心が同調したとき、自分の中に根付いた劣等感は消える。
「自分の見えている世界が人と違うからって、自分が劣っているということじゃない」
人に言われるのではなく、少しでも自分でそう思えるようになったときに。
口で言うほど簡単ではない。僕はそう思えるようになるまで、20年以上かかった。ゆっくりゆっくり、少しずつため込んだ。
そこを目指すより、道はない。
* * *
僕が話し終えると、女性は言った。
「私は彼を今まで、分かってあげれてなかった。優しい彼に甘えていました。今聞いた話で、私は今までどれだけ彼を傷つけていたのか、想像がつかない。振り返りたくない。彼がどんな思いで『自分は色盲だ』って私に告げたのか、全然分かってなかった。どうしたら悩んでる彼の力になれますか? 私にもっと色覚異常のことを教えて下さい。お願いします」
僕は言った。
「あなたが僕に言ったその言葉を、彼にそのまま伝えて下さい。彼の前で素直に、悩んで泣いてあげて下さい。色覚異常のことを、彼に教えてもらって下さい。それで分からないなら、彼は馬鹿です。
色覚異常なんて大した問題じゃない
…と気付けないなら、彼はただの大馬鹿ものです」
他人を分かってあげることなんて、本当は誰にもできない。
僕らが見ている景色を、人に見せることなんて、できないのだから。
あなたが見ている景色を、僕らが見ることなんてできないように。
それでも人は、相手のことを分かってあげようとする。
相手に分かって欲しいと、祈り続ける。
だから、どんな理由があろうとも。相手がただ自分のことを分かろうとしてくれるだけで、何となく嬉しい。
そんな人が存在するだけで、本当は幸せなことなのだ。
見えてないのは、色ではない。
見なくてはいけないものも、色ではない。
「あなたのことが知りたい」
「あなたのことを教えて下さい」
僕は、これ以上尊い愛の言葉を、今のところ知らない。