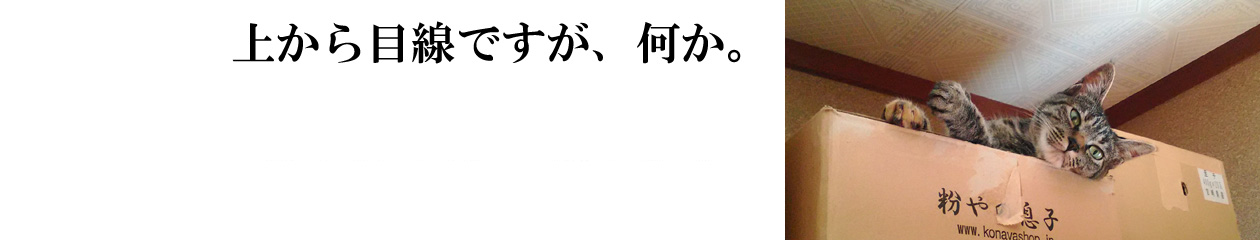犬は死んだら生ゴミになる、と。教えてくれたのは、動物病院の獣医だった。
大学生の頃。
飼っていた犬が、心臓にフィラリアという寄生虫を宿らせていた。内臓もガンに冒され、手術を行うしか生き残る方法はなかった。しかし年老いた犬の体は、手術に絶える体力がもうなかった。
結局、博打のような手術を行い、犬は命を落とした。
正確には、僕が獣医に「楽にしてやってくれ」と頼んだ。これ以上生きさせても苦しむだけだと思ったからだ。獣医にそう頼んだ僕に、電話口の後ろで母は「残酷者」と泣きながら言っていた。
犬の亡骸を引き取りに、一人で動物病院に出向いた。
冷たくなった犬を見下ろす僕に、獣医は手術内容の説明をし、続けて手術費用の説明をした。
「犬を弔ってやりたい。どうすれば良いか」
「ニ千円で、生ゴミとして引き取ってくれますよ」
獣医は答えた。詳細が印刷された紙を取り出す。準備がいいのは茶飯事なのだ。
「動物のお墓って、ないんですか」
「動物霊園のことですか。結構費用かかりますよ」
「構いません」
「提携している動物霊園はありますが、明日は確か休みだったんじゃないかな」
夏場じゃないから腐ることはないでしょうね、と獣医は付け加えた。
受付で手術費用を支払い、ダンボールで出来た棺桶を担ぎながら表へ出た。
棺桶を荷台にくくり付け、自転車を押しながら夜道を歩いた。
「死体が重いって、ほんまやねんな」
そう思った。
「お前、生ゴミやってよ」
そうも思った。
* * *
中型犬は焼くと二時間ほどで骨になる、と教えてくれたのは、動物霊園のエセ坊主だった。
結局、適当にタウンページで調べ、隣の市の動物霊園で弔ってもらうことにした。
自転車の荷台で押して行ける距離ではなく、友人が会社を休んでまで車で連れて行ってくれた。
待ち合わせの場所に行くと、頭のはげた無口そうなオッサンが立っていた。
「犬焼きたいのん、あんたらか」
「はい。よろしくお願いします」
「ワシに着いて来て」
住宅街を抜け田畑を通り、車一台通れる山道に入っていく。あたりの景色はどんどん寂しくなり、車はやがてつきあたりの広場にあるプレハブ小屋で止まった。
小屋の横に土が盛られており、てっぺんに変な形の彫像があった。後に分かったのだが、それが動物の共同墓地だった。
「動物霊園て、ここか」
友人に言った。
「みたいやな。プレハブに煙突がある。あれが火葬場やろ」
本気でやめようかやめようぜと会議している僕らに、オッサンが車を降りて問い掛けてきた。
「あんたんとこ、キリスト教?」
「いや、違いますけど」
「良かった。ワシ、賛美歌は歌われへんからな」
そう言うと、オッサンはニカッと笑った。いつ着替えたのか、袈裟まで着ていた。
「犬にお経あげるんですか?」
「仏さんの教えでは、ホンマは畜生にお経あげるの変なんやけどな。まあええやろ、あげても。犬にお経あげたるんやから、どんな経でもありがいこっちゃ」
そのお経も、このオッサンがあげるらしい。
無口そうだと思っていたオッサンは、おしゃべりで、かつ結構アバウトだった。坊主崩れの怪しさが、何だか面白くて気に入った。
しんどい現実を受け入れるには、笑うのが一番いい。
建物も墓もちゃちくて、うすら寂しい場所にある動物霊園。家族から非難轟々あびそうだったが、僕の一存でここに決めた。
お経をあげ終え、坊主が言った。
「ほな、今から遺体焼きます。中型やから、二時間ぐらいで骨になるやろ」
遺体を焼く係まで兼任らしい。
「そうですか」
「時間なかったらワシが骨拾っとくけど?」
「どこかで時間つぶします。骨は拾うつもりだったんで」
「そやな。その方がええ」
しばらくして、霊園の方角から煙があがりはじめた。
僕はそれを見て、
「あれはもう、ただの煙だ」
と思った。
* * *
それから毎年、動物霊園を訪れる。一年で一番寒い、犬を殺した日に。
動物は死ぬ間際、巣を離れ孤独な死を選ぶ本能があるという。
それは、死に行く惨めな己の姿を仲間に見せたくはないという、彼らなりのプライドなのだろう。
僕の犬も死ぬ間際、散歩の途中、家に帰ることを拒んだことがあった。その度に僕は、動こうとしない犬を抱き抱え、家に連れ帰った。
そして、行きたくもなかったであろう動物病院の手術台にあげ。
殺してくれ、と言った。
かれらの世界は、どこにあるのだろう。
動物霊園で毎年、自問自答していた。
死ねば生ゴミ扱いされ、生きていても物扱いされる。人間の都合で増やされ、人間の都合で殺される。生物としての誇りを踏みにじられ。
手術台の上で、殺される。
犬は僕を恨んでいただろうか。当たり前だが、答えは出ない。動物に、恨むなどという感情はない。動物は、何も話せない。
死ぬ間際に一言、
「お前のせいで死ぬのだ」
とでも言ってくれたなら。
償えることも、あっただろうに。
それでも、かれらは尻尾を振って。
僕らの隣で、生きてくれるのだ。
毎年動物霊園に通ってみて分かったことは、墓は死んだモノのためにあるのではない、ということだけだ。
生ゴミだろうが立派な墓だろうが、死に行くモノには何の関係もない。後に残り生きていく僕たちに、必要なだけだ。
モノに想いを残し、とまどう。
人間だからだ。
* * *
共同墓地のまわりには、沢山の花瓶が飾られてある。飼い主が添えたものだ。
その中の一つに、子供のものらしい字で書かれた花瓶がある。
『いっしょにいてくれて、ありがとう』
黒マジックのへたくそな字で、そう書かれている。
その花瓶を見るのが、僕は好きだ。想いは純粋で真っ直ぐな方が、よく伝わる。大人になると、それがなかなかできなくなる。
人はきっと、大人になるほど生きにくいようにできているのだろう。
僕には、もう書けない。でも書いてくれたことが、とても嬉しい。
花瓶に文字を書いた子供の中に、「かれらの世界」は、あり続けるだろうか。
僕の中にも、まだあるのだろうか。
そんなことを、考えたりしながら。
山を降り、また日常へと戻るのだ。