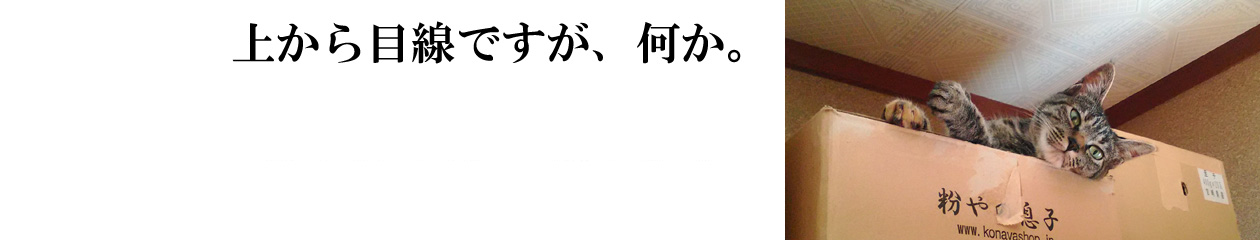先日、広大な公園のどこかで、車の鍵を落とした。
自分では落としたことに気がついていなかった。何故分かったかと言うと、「車の鍵落とした人いませんかー」と、声を張り上げ落とし主を捜していた若夫婦と子供が、目の前にいたからだ。
ポケットを叩いたら、案の定、鍵がなかった。二つに増えていたらどれだけ良かっただろう。
「すいません。その鍵、見せてもらえませんか?」
確かに、自分の車の鍵だった。
運が良い。良いけども、この運は「マイナスを0に戻すための運」である。できれば「0からプラス加算される運」で使いたかった。
「本当にありがとうございました。帰れなくなるところでした」と僕。
「良かった。滑り台の所に落ちてたんです」と奥様。
「子供と滑ったとき、落としたのかも。助かりました。あの、何かお礼でも」
若夫婦は笑顔で僕の申し出を断り、その場を後にした。
自分の運も良かった。だけどこれは、この人たちの親切心なしには成立しなかった「運」だ。公園内の人たちに、声を張り上げながら、落とし主を探して回る。中々できることではない。管理所に届けて、後は知らぬ振りで全然いい。
断られたとはいえ、何もしないのは座りが悪い。
駐車場までとって返し、財布を持って、自動販売機へ。嗜好が分からないので、当たり障りのない飲料を適当に購入。こういう時、本当は相手の喜ぶものを買ってあげたい。断られないことを考慮して、最大公約数的に購入するしかないのが悔しい(お茶系が多くなってしまうのは仕方がない)。
今度はこちらが探す番なのだが、鍵を拾ってくれた家族は、あっけなくすぐに見つかった。
「すいません、これ飲んで下さい」
「いやいやいやいやいやいやいやいや!」
ユニゾンで叫んでいた。いっせーのーでの掛け声もなく。仲の良い夫婦だ。奥さんの右手には金麦が握られていた。
「あ。金麦。良いですねー」
思わず口に出てしまったが、後から考えるとこれは良い言葉のチョイスではなかった。
「こっちがあげたかっただけだから。これはこっちの我儘だから」とか。「あちらのテーブルのお客様からです。お代はいただいております」とか。「あっちの滑り台に落ちてたんだけど、山分けしようと思って」とか。「この前読んだ新聞でね。出町柳の王将の名物店長が言ってたの。『自分が他人にしてきたことは、巡り巡って、自分の家族や子供に返ってくる。そう信じて日々生きてる』って。いい言葉でしょ? だから貰ってよ」とか。
こういうとき、親切に見合う小粋な言葉を、さっと返せる大人になりたかった。
現実は、薄ら笑いをうかべながら、ドライバーである旦那さんが我慢しているのに悪いなと思いながら飲んでいるかもしれない奥さんの金麦を揶揄したかのように受け取られかねない、見たまんまのセリフしか吐けなかった。
「どうもありがとうございました!」
夫婦のそんな言葉にも、無言で手を振るしかできない僕がいた。
何だか分からない複雑な感情に打ちひしがれる僕に向かって、当時上の吊り橋を渡っていたという奥さんと娘が言った。
「あれ、もしかしたら父ちゃんの鍵かもなー、って言うててん」
「父ちゃん、おっちょこちょいやからなー」
『追い打ち』という言葉を、この人たちは知っているのだろうか。